カレンダー
| 01 | 2026/02 | 03 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
カテゴリー
こんな映画も、レビューしてます★
最新コメント
最新記事
(08/18)
(03/10)
(07/28)
(04/13)
(04/10)
最新トラックバック
プロフィール
HN:
lulabox
性別:
男性
自己紹介:
30代の編集者/ライター。ゲイ。映画、音楽大好きですが、仕事では書く機会がなく...。ので、こちらでは趣味全開にしちゃいます。
popdorianz@yahoo.co.jp
popdorianz@yahoo.co.jp
ブログ内検索
P R
カウンター
映画はエンターテインメントでありつつも、アートフォームであって欲しいと願っています。 同じような気持ちで映画を観ているひとの慰みになれば幸いです★
原題:I Love You Phillip Morris
製作年:2009年
製作国:フランス
監督:グレン・フィカーラ、ジョン・レクア
出演:ジム・キャリー、ユアン・マクレガー、
レスリー・マン、ロドリゴ・サントロ
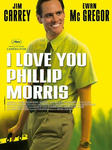
__________________________________________
実在した詐欺師の半生を描いた作品。
全体的にコメディタッチなのでうっかりフィクションと思いがちだが、
劇中で繰り広げる詐欺から脱獄の手口まで、ほぼ事実というのがすごい。
その詐欺師、スティーヴン・ジェイ・ラッセルという人物には、
警察官としてのキャリアがあり、就業当時、データベース化されている
国民のプロファイルを、何らかのかたちで改ざんする術を身につけたらしい。
彼の華麗なる犯罪歴は90年代に集中しているようだが、
警察機関が本格的に導入したシステム環境を、
見事に悪用しきったケースなのだろう。
犯罪歴のある人間がまんまと大会社の要職にありつき、
信用を得たところで横領を働くなんて、すごすぎる。
その天才的な犯罪術は獄中でも存分に発揮され、
驚くほど大胆な手口で、幾度も脱獄に成功している。
彼の天性と、ずさんな米国の管理システムが絡み合って生まれた、
犯罪の芸術と呼んで差し支えないだろう。
この作品は、彼の半生を追ったノンフィクション書籍を
ベースに製作されている。
原作の論調は恐らく、一連の犯罪の由来を彼の不幸な幼少期に置き、
好意的に、アンチヒーロー化しているのではないかと思う。
実際彼は殺人などの残虐行為に走ったわけではなく、
その知性をまっとうな方向に発揮していたら、
それなりの実績も残せた人物であるに違いない。
これはこれで「あり」な視点だが、
その大胆不敵な犯罪の分析と、統合失調的なパーソナリティに焦点を当てた、
ハードボイルドな作品も作れそうな題材かと思う。
個人的には、今年初めて劇場で見た作品。
ゲイものだったので彼氏を伴って出かけたが、
映画館にはあまりゲイをみかけなかった。
同列によく笑う妙齢のノンケカップルがいたが、
「こんなつまんないとこで、そんなに笑う?」という感じで、
まだまだツボがおわかりになっていないご様子。
使用されている音楽にもオカマ心に響くものは特になく、
全体的に、ゲイものならではの演出は控えめだ。
そんな中絶賛したいのは、ユアン・マクレガー。
もともとナイーヴな青年役のイメージが強い彼だが、
ウケのゲイにあるひとつの類型を、非常によく研究してきていた。
身の回りにゲイがいない人の目にかかると、
サラッと流されそうなのが心配なほどの、名演技。
僕の目には、途中から友だち(外専)の姿が完全にオーバーラップしており、
「あ~いるいる、こういう子!」と、思わず唸ってしまった。
感情の発露から小首の傾げ方まで、
成り切るというか、憑依の域に達している感じなのである。
思わず、役者としての彼を強くリスペクトした次第。
製作年:2009年
製作国:フランス
監督:グレン・フィカーラ、ジョン・レクア
出演:ジム・キャリー、ユアン・マクレガー、
レスリー・マン、ロドリゴ・サントロ
__________________________________________
実在した詐欺師の半生を描いた作品。
全体的にコメディタッチなのでうっかりフィクションと思いがちだが、
劇中で繰り広げる詐欺から脱獄の手口まで、ほぼ事実というのがすごい。
その詐欺師、スティーヴン・ジェイ・ラッセルという人物には、
警察官としてのキャリアがあり、就業当時、データベース化されている
国民のプロファイルを、何らかのかたちで改ざんする術を身につけたらしい。
彼の華麗なる犯罪歴は90年代に集中しているようだが、
警察機関が本格的に導入したシステム環境を、
見事に悪用しきったケースなのだろう。
犯罪歴のある人間がまんまと大会社の要職にありつき、
信用を得たところで横領を働くなんて、すごすぎる。
その天才的な犯罪術は獄中でも存分に発揮され、
驚くほど大胆な手口で、幾度も脱獄に成功している。
彼の天性と、ずさんな米国の管理システムが絡み合って生まれた、
犯罪の芸術と呼んで差し支えないだろう。
この作品は、彼の半生を追ったノンフィクション書籍を
ベースに製作されている。
原作の論調は恐らく、一連の犯罪の由来を彼の不幸な幼少期に置き、
好意的に、アンチヒーロー化しているのではないかと思う。
実際彼は殺人などの残虐行為に走ったわけではなく、
その知性をまっとうな方向に発揮していたら、
それなりの実績も残せた人物であるに違いない。
これはこれで「あり」な視点だが、
その大胆不敵な犯罪の分析と、統合失調的なパーソナリティに焦点を当てた、
ハードボイルドな作品も作れそうな題材かと思う。
個人的には、今年初めて劇場で見た作品。
ゲイものだったので彼氏を伴って出かけたが、
映画館にはあまりゲイをみかけなかった。
同列によく笑う妙齢のノンケカップルがいたが、
「こんなつまんないとこで、そんなに笑う?」という感じで、
まだまだツボがおわかりになっていないご様子。
使用されている音楽にもオカマ心に響くものは特になく、
全体的に、ゲイものならではの演出は控えめだ。
そんな中絶賛したいのは、ユアン・マクレガー。
もともとナイーヴな青年役のイメージが強い彼だが、
ウケのゲイにあるひとつの類型を、非常によく研究してきていた。
身の回りにゲイがいない人の目にかかると、
サラッと流されそうなのが心配なほどの、名演技。
僕の目には、途中から友だち(外専)の姿が完全にオーバーラップしており、
「あ~いるいる、こういう子!」と、思わず唸ってしまった。
感情の発露から小首の傾げ方まで、
成り切るというか、憑依の域に達している感じなのである。
思わず、役者としての彼を強くリスペクトした次第。
PR
原題:頤和園
製作年:2006年
製作国:中国/フランス
監督:ロウ・イエ
出演:ハオ・レイ、グオ・シャオドン、フー・リン、
チャン・シャンミン、ツアン・メイホイツ
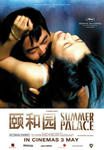
_________________________
中華映画はここのところご無沙汰だったのだが、
先日この監督の『ふたりの人魚』を観た。
本気で物語を描くことからは、少し距離を置いている感じだったが、
作品性があったので興味が湧き、本作を観てみようと思った。
天安門事件の渦中に大学生時代を過ごした恋人同士を描いているのだが、
当のふたり、若さとエネルギーを、
民主化に向けさほど注ぎ込んだクチでもない。
ただがむしゃらに何かに向かおうとする情熱だけは持ち合わせており、
そこで共鳴し合って結ばれただけ。時代に巻き込まれたのである。
政情に不満や関心の薄い時代であれば、
何か別の表現に向かう同志であったに違いないのだ。
たくさんの若さや才能を無駄にしてしまうのが、
政情不安やその先にある戦争の怖さ。
日本の安保闘争も然りだが、理想実現への行動が挫かれた後には、
”シラケの時代”が待っている。
天安門事件の混乱の中、男と別れた主人公の女は、
次々に別の男と関係を結ぶようになる。
思想を深めることが無駄だと「わかってしまった」以上、
最も手っ取り早いやり方で、フィジカルに自分を伝えようとすることだけが、
彼女の情熱の向かう先なのだ。
そうして「愛される」ことについては未成熟なまま齢を重ねた彼女は、
いつも心の拠り所であった...つまり知らず知らずのうちに
心の中で理想化していた...男と再会し、
ふたりが同じように、砂を噛むような日々を送ってきたことを
思い知るのである。
「目的なく孤独に生きる」とは、劇中のセリフだが、
本作の狙いは、登場人物と同世代の人々の心にぽっかりと空いた
空虚な穴を、丹念に描くことにあったようだ。
観ることで浄化された中国人もいるだろう。
またある程度の普遍性も持ち合わせており、
日本人の私にも共感できる場面が、たくさんあった。
それにしても、中国の近現代を描いた映画は、単純に興味深い。
ウォン・カーウァイが90年代の香港を、
スタイリッシュな映像に刻み込んだのには感動したが、
それ以前のものとなると、レスリー・チャンが出演している
80年代の娯楽映画ぐらいしか観たことがないのだ。
ブルース・リーやジャッキー・チェンのアクション映画には
いまのところ興味ないし...。
本作で描かれた、中国学生寮の世界は初めて目にするし、
「ヤリマンはいるのね、やっぱり」と思ったりもして、
すべてが新鮮に見えた。
『ふたりの人魚』では、「河」を舞台に現代の若者の生活を
カッコ良く切り取っていたし、この監督の新作が、今後も楽しみ。
製作年:2006年
製作国:中国/フランス
監督:ロウ・イエ
出演:ハオ・レイ、グオ・シャオドン、フー・リン、
チャン・シャンミン、ツアン・メイホイツ
_________________________
中華映画はここのところご無沙汰だったのだが、
先日この監督の『ふたりの人魚』を観た。
本気で物語を描くことからは、少し距離を置いている感じだったが、
作品性があったので興味が湧き、本作を観てみようと思った。
天安門事件の渦中に大学生時代を過ごした恋人同士を描いているのだが、
当のふたり、若さとエネルギーを、
民主化に向けさほど注ぎ込んだクチでもない。
ただがむしゃらに何かに向かおうとする情熱だけは持ち合わせており、
そこで共鳴し合って結ばれただけ。時代に巻き込まれたのである。
政情に不満や関心の薄い時代であれば、
何か別の表現に向かう同志であったに違いないのだ。
たくさんの若さや才能を無駄にしてしまうのが、
政情不安やその先にある戦争の怖さ。
日本の安保闘争も然りだが、理想実現への行動が挫かれた後には、
”シラケの時代”が待っている。
天安門事件の混乱の中、男と別れた主人公の女は、
次々に別の男と関係を結ぶようになる。
思想を深めることが無駄だと「わかってしまった」以上、
最も手っ取り早いやり方で、フィジカルに自分を伝えようとすることだけが、
彼女の情熱の向かう先なのだ。
そうして「愛される」ことについては未成熟なまま齢を重ねた彼女は、
いつも心の拠り所であった...つまり知らず知らずのうちに
心の中で理想化していた...男と再会し、
ふたりが同じように、砂を噛むような日々を送ってきたことを
思い知るのである。
「目的なく孤独に生きる」とは、劇中のセリフだが、
本作の狙いは、登場人物と同世代の人々の心にぽっかりと空いた
空虚な穴を、丹念に描くことにあったようだ。
観ることで浄化された中国人もいるだろう。
またある程度の普遍性も持ち合わせており、
日本人の私にも共感できる場面が、たくさんあった。
それにしても、中国の近現代を描いた映画は、単純に興味深い。
ウォン・カーウァイが90年代の香港を、
スタイリッシュな映像に刻み込んだのには感動したが、
それ以前のものとなると、レスリー・チャンが出演している
80年代の娯楽映画ぐらいしか観たことがないのだ。
ブルース・リーやジャッキー・チェンのアクション映画には
いまのところ興味ないし...。
本作で描かれた、中国学生寮の世界は初めて目にするし、
「ヤリマンはいるのね、やっぱり」と思ったりもして、
すべてが新鮮に見えた。
『ふたりの人魚』では、「河」を舞台に現代の若者の生活を
カッコ良く切り取っていたし、この監督の新作が、今後も楽しみ。
原題:Filth and Wisdom WONDER LUST
製作年:2008年
製作国:イギリス
監督:マドンナ
出演:ユージン・ハッツ、ホリー・ウェストン、
ヴィッキー・マクルア

____________________________________
歌手としては、これ以上ないほど素晴らしいキャリアを
築いたスーパースター、マドンナ。
同時進行で女優としても成功を目指し、チャレンジを繰り返してきたが、
満を期して望んだ『エビータ』でも、オスカー候補にはなれずじまい。
そろそろあきらめたのかと思いきや、今度は監督業に乗り出してきた。
といっても、私はマドンナが嫌いではない。
まず彼女は並外れた努力家である。
そして映画であれなんであれ、アートへのリスペクトを怠らない、
聡明な一面を持っている。
女優として有名になりたいのと同じくらい、
純粋な映画好きでもあるのだろう。
きっと忙しさの合間を縫い、新旧のさまざまな作品を観ているに違いない。
そんな彼女の処女作ということで期待したのだが、
まず彼女が選んだ作品のテーマに、ややぐったり。
自分の選んだ表現法で世の中と関わろうとする、
アウトローな若者たちを描いた青春映画で、
ターゲットも10~20代前半までに限定された感が否めない。
マドンナは映画監督としてピチピチの新人なのだから、
このぐらいハチャメチャなテーマで映画を撮るのは悪くない。
しかしスキャンダラスな行状で
世の注目を集めてきた悪名高き彼女が、
「これが若者の流儀なのよ! クールでしょ!」とでもいわんばかりに、
えげつない演出を詰め込んできたら...。
そんな悪い予感を抱かないでもなかった。
しかし内容は思ったよりもポジティヴ。
「どんなに最低の状況でも、知的好奇心を失うな」といった
メッセージや、哲学的な問いかけが全編に詰め込まれ、
やや説教臭さが感じられるほどだ。
また突然、おしゃれ広告ぽい撮影技法を挿入するなど、
映像面での挑戦が散見される。
淡々と撮るプロット重視の新進監督が目立つ昨今において、
フックの多い映像には気骨が感じられた。
ただやはり、どうにも我慢できなかったのが、
主人公であるダメ男の妄執的なエゴイズム。
売れないバンドマン役を演じるユージン・ハッツは、
実際にニューヨークでカルト的な人気を誇るバンドのヴォーカリストで、
カルチャー・アイコンとして注目を集める存在らしいが、
私には馬面の白人男にしか見えなかった。
マドンナはショウビズ界を牛耳る白人男たちに
断固対抗してきた存在で、
その革新性を高く評価し続けたかったのだが...。
この映画の主人公のようなタイプが大金を掴むと、
独善的な価値観を押し付ける害虫のような存在になるのではないのだろうか?
それとも、彼のようなタイプは根が繊細で知的だから、
そうはならないのだろうか?
そこら辺の違いが、私には明確にわからない。
マドンナのライブツアードキュメントはすごく面白いのだが、
その中にツアーダンサーを決めるオーディション風景があった。
自己顕示欲の強いアメリカの若者の中でも、
選りすぐりのハリネズミ連中が集結、といった趣で、
間違っても近寄りたくない現場だが、
マドンナはそうした若者たちに、若き日の自分の姿を重ね合わせ、
強い愛情を感じているようだ。
今回の作品内の、スクリーンからはみ出そうな「俺、俺、俺」節を見るだけでも、
それは明白である。
ただそうした「我執」というのは、全世界の人口の中でもごく一部の、
表現に向かっている人間にとってだけ必要不可欠なもので、
組織に属し生計を立てる者にとっては、
注意深く取り扱わなくてはならない危険物なのである。
もう次回作の製作も決まっているという話だが、
本作で感じられた観衆との距離感を微妙に修正する努力をしないと、
スターの手慰みに終わってしまう危険を感じさせた1本である。
製作年:2008年
製作国:イギリス
監督:マドンナ
出演:ユージン・ハッツ、ホリー・ウェストン、
ヴィッキー・マクルア
____________________________________
歌手としては、これ以上ないほど素晴らしいキャリアを
築いたスーパースター、マドンナ。
同時進行で女優としても成功を目指し、チャレンジを繰り返してきたが、
満を期して望んだ『エビータ』でも、オスカー候補にはなれずじまい。
そろそろあきらめたのかと思いきや、今度は監督業に乗り出してきた。
といっても、私はマドンナが嫌いではない。
まず彼女は並外れた努力家である。
そして映画であれなんであれ、アートへのリスペクトを怠らない、
聡明な一面を持っている。
女優として有名になりたいのと同じくらい、
純粋な映画好きでもあるのだろう。
きっと忙しさの合間を縫い、新旧のさまざまな作品を観ているに違いない。
そんな彼女の処女作ということで期待したのだが、
まず彼女が選んだ作品のテーマに、ややぐったり。
自分の選んだ表現法で世の中と関わろうとする、
アウトローな若者たちを描いた青春映画で、
ターゲットも10~20代前半までに限定された感が否めない。
マドンナは映画監督としてピチピチの新人なのだから、
このぐらいハチャメチャなテーマで映画を撮るのは悪くない。
しかしスキャンダラスな行状で
世の注目を集めてきた悪名高き彼女が、
「これが若者の流儀なのよ! クールでしょ!」とでもいわんばかりに、
えげつない演出を詰め込んできたら...。
そんな悪い予感を抱かないでもなかった。
しかし内容は思ったよりもポジティヴ。
「どんなに最低の状況でも、知的好奇心を失うな」といった
メッセージや、哲学的な問いかけが全編に詰め込まれ、
やや説教臭さが感じられるほどだ。
また突然、おしゃれ広告ぽい撮影技法を挿入するなど、
映像面での挑戦が散見される。
淡々と撮るプロット重視の新進監督が目立つ昨今において、
フックの多い映像には気骨が感じられた。
ただやはり、どうにも我慢できなかったのが、
主人公であるダメ男の妄執的なエゴイズム。
売れないバンドマン役を演じるユージン・ハッツは、
実際にニューヨークでカルト的な人気を誇るバンドのヴォーカリストで、
カルチャー・アイコンとして注目を集める存在らしいが、
私には馬面の白人男にしか見えなかった。
マドンナはショウビズ界を牛耳る白人男たちに
断固対抗してきた存在で、
その革新性を高く評価し続けたかったのだが...。
この映画の主人公のようなタイプが大金を掴むと、
独善的な価値観を押し付ける害虫のような存在になるのではないのだろうか?
それとも、彼のようなタイプは根が繊細で知的だから、
そうはならないのだろうか?
そこら辺の違いが、私には明確にわからない。
マドンナのライブツアードキュメントはすごく面白いのだが、
その中にツアーダンサーを決めるオーディション風景があった。
自己顕示欲の強いアメリカの若者の中でも、
選りすぐりのハリネズミ連中が集結、といった趣で、
間違っても近寄りたくない現場だが、
マドンナはそうした若者たちに、若き日の自分の姿を重ね合わせ、
強い愛情を感じているようだ。
今回の作品内の、スクリーンからはみ出そうな「俺、俺、俺」節を見るだけでも、
それは明白である。
ただそうした「我執」というのは、全世界の人口の中でもごく一部の、
表現に向かっている人間にとってだけ必要不可欠なもので、
組織に属し生計を立てる者にとっては、
注意深く取り扱わなくてはならない危険物なのである。
もう次回作の製作も決まっているという話だが、
本作で感じられた観衆との距離感を微妙に修正する努力をしないと、
スターの手慰みに終わってしまう危険を感じさせた1本である。
原題:8 femmes
製作年:2002年
製作国:フランス
監督:フランソワ・オゾン
出演;ダニエル・ダリュ―、カトリーヌ・ドヌーヴ、イザベル・ユペール、
エマニュエル・ベアール、ファニー・アルダン、ヴィルジニー・ルドワイヤン、
リュディヴィーヌ・サニエ、フィルミーヌ・リシャール

______________________
この映画をはじめて観たのはもうだいぶ前の事だが、
それほど強い印象をもったわけではない。
しかしダビングしたものを繰り返し観ているので、
やはり好きな映画ということになる。
独りでご飯を食べる時なんかには、軽くて、BGVに最適なのだ。
オゾン監督の映画にはちょっと斜めに構えたところがあって、
僕が本当に好きなタイプの監督ではない。
しかしこの映画には、8人もの女優が登場し、大立ち回りを繰り広げる。
女性上位の映画なら大好き!
僕にとって「女優」は、映画の中で非常に重要な存在なのだ。
ただの女に興味はないが、
女優~ドヌ-ヴ、ユペールのような~という存在に
賛辞を贈ることは、決して惜しまない。
映画の華として、なくてはならない存在だと思っている。
きっとオゾン監督もそうなのだろう。だからこの映画には強く共感できる。
ということで最近、この映画の限定DVDボックスを入手した。
本編は何度も観ているので、その世界をより深く識ることのできる
ボーナスディスクが目当てだ。
インタビューでは、8人の女優が製作秘話を語る。
その中からオゾン監督の姿が否応無しに浮かび上がってくるのだが、
面白かったのはドヌ-ヴの話。
そもそも役柄に不満が大きかったようで、
愚痴が口を突いて出るという感じなのだが、
その矛先はオゾン監督の演出スタンスへと向かう。
これは女優たちの意見がほぼ一致しているので事実なのだろうが、
撮影現場でのオゾン監督は「優しい暴君」のようで、怒鳴りこそしないが、
女優たちに独自の解釈や、自由な演技を認めないという。
輝かしいキャリアに相応しいプライドを持つ大女優にとって、
それなりの屈辱であることは想像に難くない。
またウーマンリヴの時代を駆け抜けてきた彼女にとって、
「女優」ではなく「女性」そのものを賞賛しない態度は、
腹に据えかねるものがあるらしい。
他の女優が朗らかに「これは女性を賛美した映画よ」と語るのとは対照的に、
ドヌーヴだけが監督への不信感を露にする。
そこに彼女の屈託が見えるようで、却って好印象を抱いた。
闘志を持たない女優に、スクリーンを飾る資格などないのだから。
屈折した役柄含め、個人的に最も気に入ったのはイザベル・ユペール。
それまであまり注目していなかったのだが、
この映画を観てから一気にファンになり、
主演作を片っ端から漁るようになった。
それほど美しくはないが、目の離せない個性を持っていて、
役者としての魅力は抜きんでている。
ここまでコメディエンヌぶりを発揮した出演作はほかにないようだが、
エキセントリックで大げさな演技が最高。
特にファニー・アルダンとの初対面シーンが傑作なのだが、
現場ではお互い乗り過ぎたようで、顔を見合わせるとつい笑ってしまう。
そんな楽しいやり取りが、NG集にはたくさん収められている。
この映画には推理劇、喜劇のほかにミュージカルの要素があり、
8人の女優がそれぞれ見せ場を持っているのだが、
選曲は監督自身が、フレンチポップス史上から行った。
僕がわかったのはユペールが歌うアルディの歌だけなのだが、
ダリダやシェイラなんかの歌も入っていたらしい。
残念なのは振付。コレオグラファーとしては素人の、
俳優による振り付けなのだが、
それだけで観賞に耐えうるものが1本もないというのは、なんとも残念。
まぁ女優=プロの踊り手ではないので仕方がない、というのもあるが、
オゾン監督からのオーダーは「誰にでも真似できる簡単な振り」だったとか。
しかし「誰もが真似する振付」というのは
まず「誰もがあこがれる振付」でなくては、と思うのだが。
メイキングシーンから得た重要な情報として、
この作品の下敷きの一つに、
ジョージ・キューカー監督の『女たち』という
映画があることがわかったのだが、
日本未公開で、字幕付きの映像ソフトも販売されていない。
同じく女性ばかりのキャストで撮影されており、
ジョーン・クロフォード辺りが出演しているらしいので、ぜひ観たいのだが...。
この映画のプロモが大々的に行われている間にも実現しなかったので、
今後も無理だろうか。
製作年:2002年
製作国:フランス
監督:フランソワ・オゾン
出演;ダニエル・ダリュ―、カトリーヌ・ドヌーヴ、イザベル・ユペール、
エマニュエル・ベアール、ファニー・アルダン、ヴィルジニー・ルドワイヤン、
リュディヴィーヌ・サニエ、フィルミーヌ・リシャール
______________________
この映画をはじめて観たのはもうだいぶ前の事だが、
それほど強い印象をもったわけではない。
しかしダビングしたものを繰り返し観ているので、
やはり好きな映画ということになる。
独りでご飯を食べる時なんかには、軽くて、BGVに最適なのだ。
オゾン監督の映画にはちょっと斜めに構えたところがあって、
僕が本当に好きなタイプの監督ではない。
しかしこの映画には、8人もの女優が登場し、大立ち回りを繰り広げる。
女性上位の映画なら大好き!
僕にとって「女優」は、映画の中で非常に重要な存在なのだ。
ただの女に興味はないが、
女優~ドヌ-ヴ、ユペールのような~という存在に
賛辞を贈ることは、決して惜しまない。
映画の華として、なくてはならない存在だと思っている。
きっとオゾン監督もそうなのだろう。だからこの映画には強く共感できる。
ということで最近、この映画の限定DVDボックスを入手した。
本編は何度も観ているので、その世界をより深く識ることのできる
ボーナスディスクが目当てだ。
インタビューでは、8人の女優が製作秘話を語る。
その中からオゾン監督の姿が否応無しに浮かび上がってくるのだが、
面白かったのはドヌ-ヴの話。
そもそも役柄に不満が大きかったようで、
愚痴が口を突いて出るという感じなのだが、
その矛先はオゾン監督の演出スタンスへと向かう。
これは女優たちの意見がほぼ一致しているので事実なのだろうが、
撮影現場でのオゾン監督は「優しい暴君」のようで、怒鳴りこそしないが、
女優たちに独自の解釈や、自由な演技を認めないという。
輝かしいキャリアに相応しいプライドを持つ大女優にとって、
それなりの屈辱であることは想像に難くない。
またウーマンリヴの時代を駆け抜けてきた彼女にとって、
「女優」ではなく「女性」そのものを賞賛しない態度は、
腹に据えかねるものがあるらしい。
他の女優が朗らかに「これは女性を賛美した映画よ」と語るのとは対照的に、
ドヌーヴだけが監督への不信感を露にする。
そこに彼女の屈託が見えるようで、却って好印象を抱いた。
闘志を持たない女優に、スクリーンを飾る資格などないのだから。
屈折した役柄含め、個人的に最も気に入ったのはイザベル・ユペール。
それまであまり注目していなかったのだが、
この映画を観てから一気にファンになり、
主演作を片っ端から漁るようになった。
それほど美しくはないが、目の離せない個性を持っていて、
役者としての魅力は抜きんでている。
ここまでコメディエンヌぶりを発揮した出演作はほかにないようだが、
エキセントリックで大げさな演技が最高。
特にファニー・アルダンとの初対面シーンが傑作なのだが、
現場ではお互い乗り過ぎたようで、顔を見合わせるとつい笑ってしまう。
そんな楽しいやり取りが、NG集にはたくさん収められている。
この映画には推理劇、喜劇のほかにミュージカルの要素があり、
8人の女優がそれぞれ見せ場を持っているのだが、
選曲は監督自身が、フレンチポップス史上から行った。
僕がわかったのはユペールが歌うアルディの歌だけなのだが、
ダリダやシェイラなんかの歌も入っていたらしい。
残念なのは振付。コレオグラファーとしては素人の、
俳優による振り付けなのだが、
それだけで観賞に耐えうるものが1本もないというのは、なんとも残念。
まぁ女優=プロの踊り手ではないので仕方がない、というのもあるが、
オゾン監督からのオーダーは「誰にでも真似できる簡単な振り」だったとか。
しかし「誰もが真似する振付」というのは
まず「誰もがあこがれる振付」でなくては、と思うのだが。
メイキングシーンから得た重要な情報として、
この作品の下敷きの一つに、
ジョージ・キューカー監督の『女たち』という
映画があることがわかったのだが、
日本未公開で、字幕付きの映像ソフトも販売されていない。
同じく女性ばかりのキャストで撮影されており、
ジョーン・クロフォード辺りが出演しているらしいので、ぜひ観たいのだが...。
この映画のプロモが大々的に行われている間にも実現しなかったので、
今後も無理だろうか。
原題:Vidas Privadas
製作年:2001年
製作国:アルゼンチン/スペイン
監督:フィト・パエス
出演:セシリア・ロス、ガエル・ガルシア・ベルナル、
ルイス・シエンブロウスキー、ドロレス・フォンシ、カローナ・レイナ

_________________________________________
過去のトラウマにより、恋愛やセックスができなくなった女性が、
「お気に入りの声」をもつ男性と出逢ったことで、
再び愛情と希望に満ちた人生を取り戻しはじめる……、
というあらすじの、なかなかエキセントリックな作品。
しかし本当に訴えたかったのは、
彼女の「過去のトラウマ」自体なのではないかと思う。
なぜならそれは、単なる創作上の設定ではなく、史実だからだ。
僕は全く知らなかったのだが、
アルゼンチンでは70年代後半に軍事クーデターがあり、
以後7年間もの長きに渡って、軍部による独裁政治が敷かれてしまった。
さまざまな人権弾圧が行われ、行方不明者は3万人以上にも及ぶという。
70年代後半~80年代前半に20代だった人(この映画の主人公もそう)は、
この映画の製作時にはまだ40代という若さ。
同国内では生々しい記憶として残っていても当然なのだ。
日本に住んでいると、さほど齢の離れていない人が、
政治に人生を左右され、大きなトラウマを抱えているという事実が
実感としてわからないのだが、
それは生まれた時代がたまたま良かったというだけ。
もし世界大戦時に生を受けていたら、また第二次世界大戦で
日本が敗戦国になっていなかったとしたら、と思うと
当然他人事ではない。
ドイツナチスに関する映画は、
これまでに数え切れないほど創られてきたが、
アルゼンチンの映画人は、
今ようやくその重い口を開きはじたところなのかもしれない。
しかしこの映画の素晴らしさは、僕のように無知な者が、
観終わった後で史実を調べることにより、
さらに理解が深まるよう、注意深く作られているところ。
現代に生きる人間が映画によせる類いの関心を見越しているのが
クールだし、監督はエンターテイナーでもあると思う。
と思ったらフィト・パエスは国内でも有名な歌手で、これが初長篇作、
しかも主演のセシリア・ロスの夫でもあるというのだから、驚いた。
それにしてもラティーノ/ラティーナの生き方には、
やはりエキゾチズムがそそられる。
主人公にしても、トラウマを背負っていながら自慰に積極的なのだから、
性そのものにはオープンなのだ。
日本人の感覚からすると、性全体に背を向けてしまう方が、
無難な描き方なのでは? と思ってしまう。その相違が面白い。
一時期アルモドヴァルの緒作品や、
ビクトリア・アブリルの出演作品などを
片っ端から観ていた時期があったのだが、
もっともっとスペインやラテン・アメリカの映画が観たい。
その為に、ガエル・ガルシア・ベルナルや、ぺネロペ・クルス
といった俳優の活躍に期待したい。
製作年:2001年
製作国:アルゼンチン/スペイン
監督:フィト・パエス
出演:セシリア・ロス、ガエル・ガルシア・ベルナル、
ルイス・シエンブロウスキー、ドロレス・フォンシ、カローナ・レイナ
_________________________________________
過去のトラウマにより、恋愛やセックスができなくなった女性が、
「お気に入りの声」をもつ男性と出逢ったことで、
再び愛情と希望に満ちた人生を取り戻しはじめる……、
というあらすじの、なかなかエキセントリックな作品。
しかし本当に訴えたかったのは、
彼女の「過去のトラウマ」自体なのではないかと思う。
なぜならそれは、単なる創作上の設定ではなく、史実だからだ。
僕は全く知らなかったのだが、
アルゼンチンでは70年代後半に軍事クーデターがあり、
以後7年間もの長きに渡って、軍部による独裁政治が敷かれてしまった。
さまざまな人権弾圧が行われ、行方不明者は3万人以上にも及ぶという。
70年代後半~80年代前半に20代だった人(この映画の主人公もそう)は、
この映画の製作時にはまだ40代という若さ。
同国内では生々しい記憶として残っていても当然なのだ。
日本に住んでいると、さほど齢の離れていない人が、
政治に人生を左右され、大きなトラウマを抱えているという事実が
実感としてわからないのだが、
それは生まれた時代がたまたま良かったというだけ。
もし世界大戦時に生を受けていたら、また第二次世界大戦で
日本が敗戦国になっていなかったとしたら、と思うと
当然他人事ではない。
ドイツナチスに関する映画は、
これまでに数え切れないほど創られてきたが、
アルゼンチンの映画人は、
今ようやくその重い口を開きはじたところなのかもしれない。
しかしこの映画の素晴らしさは、僕のように無知な者が、
観終わった後で史実を調べることにより、
さらに理解が深まるよう、注意深く作られているところ。
現代に生きる人間が映画によせる類いの関心を見越しているのが
クールだし、監督はエンターテイナーでもあると思う。
と思ったらフィト・パエスは国内でも有名な歌手で、これが初長篇作、
しかも主演のセシリア・ロスの夫でもあるというのだから、驚いた。
それにしてもラティーノ/ラティーナの生き方には、
やはりエキゾチズムがそそられる。
主人公にしても、トラウマを背負っていながら自慰に積極的なのだから、
性そのものにはオープンなのだ。
日本人の感覚からすると、性全体に背を向けてしまう方が、
無難な描き方なのでは? と思ってしまう。その相違が面白い。
一時期アルモドヴァルの緒作品や、
ビクトリア・アブリルの出演作品などを
片っ端から観ていた時期があったのだが、
もっともっとスペインやラテン・アメリカの映画が観たい。
その為に、ガエル・ガルシア・ベルナルや、ぺネロペ・クルス
といった俳優の活躍に期待したい。

