カレンダー
| 01 | 2026/02 | 03 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
カテゴリー
こんな映画も、レビューしてます★
最新コメント
最新記事
(08/18)
(03/10)
(07/28)
(04/13)
(04/10)
最新トラックバック
プロフィール
HN:
lulabox
性別:
男性
自己紹介:
30代の編集者/ライター。ゲイ。映画、音楽大好きですが、仕事では書く機会がなく...。ので、こちらでは趣味全開にしちゃいます。
popdorianz@yahoo.co.jp
popdorianz@yahoo.co.jp
ブログ内検索
P R
カウンター
映画はエンターテインメントでありつつも、アートフォームであって欲しいと願っています。 同じような気持ちで映画を観ているひとの慰みになれば幸いです★
原題:TROP BELLE POUR TOI
製作年:1989年
製作国:フランス
監督:ベルトラン・ブリエ
出演:ジョジアーヌ・バラスコ、ジェラール・ドパルデュー、
キャロル・ブーケ
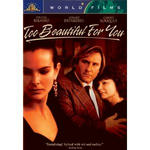
________________________
「愛欲」や「価値観の反転」というテーマを、
ちょっと面白い手法で描いている映画。
映画を作るにあたって、
登場人物の感情の流れを画面でどう表現していくかは、
演出面での大きな分かれ路になりえるかと思うが、
本作は「俳優に台詞で喋らせる」方法を多用する。
普通の映画ならモノローグなどで表現する心の動きを、
ペラペラと口に出すところが何とも奇妙であり、独特なのだ。
ベルトラン・ブリエ監督の出自はヌーヴェルバーグ運動にあるので、
こうした、ある意味不自然に見える脚本作りはお手の物なのだろう。
だがデティールに流れ過ぎているわけではなく、
映画としての力強さもきちんと備わっているので、好感度は高い。
惜しむらくは、物語が後半へ進むにつれ、
展開がやや凡庸になっていくところ。
現実と妄想が入り混じったようなシークエンスを紡ぐことで、
平凡な不倫物語たることを拒否するのだが、
かといってキャラクターを過度に美化するヒロイズムもまた、
受け入れられなかった様子だ。
結末にはどうしても中途半端な印象が残ったが、
前半の非凡な輝きのお陰で、全体が許せてしまう。
なんともチャーミングな作品である。
同じヌーヴェルバーグ出身でも、
例えばゴダールの80年代作品なんて、つまらなくてつまらなくて、
「何でもありがたがる信者だけに見せとけば?」と掃き捨てたくなる。
しかしベルトラン・ブリエには、
若い世代にアピールし続けられるバランス感覚が
備わっているように感じられた。
近年の作品も観てみよう、と思った次第。
製作年:1989年
製作国:フランス
監督:ベルトラン・ブリエ
出演:ジョジアーヌ・バラスコ、ジェラール・ドパルデュー、
キャロル・ブーケ
________________________
「愛欲」や「価値観の反転」というテーマを、
ちょっと面白い手法で描いている映画。
映画を作るにあたって、
登場人物の感情の流れを画面でどう表現していくかは、
演出面での大きな分かれ路になりえるかと思うが、
本作は「俳優に台詞で喋らせる」方法を多用する。
普通の映画ならモノローグなどで表現する心の動きを、
ペラペラと口に出すところが何とも奇妙であり、独特なのだ。
ベルトラン・ブリエ監督の出自はヌーヴェルバーグ運動にあるので、
こうした、ある意味不自然に見える脚本作りはお手の物なのだろう。
だがデティールに流れ過ぎているわけではなく、
映画としての力強さもきちんと備わっているので、好感度は高い。
惜しむらくは、物語が後半へ進むにつれ、
展開がやや凡庸になっていくところ。
現実と妄想が入り混じったようなシークエンスを紡ぐことで、
平凡な不倫物語たることを拒否するのだが、
かといってキャラクターを過度に美化するヒロイズムもまた、
受け入れられなかった様子だ。
結末にはどうしても中途半端な印象が残ったが、
前半の非凡な輝きのお陰で、全体が許せてしまう。
なんともチャーミングな作品である。
同じヌーヴェルバーグ出身でも、
例えばゴダールの80年代作品なんて、つまらなくてつまらなくて、
「何でもありがたがる信者だけに見せとけば?」と掃き捨てたくなる。
しかしベルトラン・ブリエには、
若い世代にアピールし続けられるバランス感覚が
備わっているように感じられた。
近年の作品も観てみよう、と思った次第。
PR
原題:THE TIMES OF HARVEY MILK
製作年:1984年
製作国:アメリカ
監督:ロバート・エプスタイン

________________________
先日、東京都知事の石原慎太郎があからさまなゲイ差別発言をしたことが、
ネットニュースで配信された。
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20101208ddm041010103000c.html
これを受け、怒りを表明するゲイの発言が、これまたネット上に数多く噴出した。
一般のゲイ・ピープルによる憤怒を、数多く目にする機会があったのは、
僕自身がゲイだから。
SNSなどで繋がっている人たちの大半をゲイ・ピープルが占めているため、
彼らの生の声を、他の人よりも多く目にすることができたというわけだ。
なんて客観的態度を見せびらかしていると、
「じゃあアンタはどう思っているんだ」と問い質されそうなので、率直に言おう。
僕は「よくぞ言ってくれたなぁ」と感心している。
発言内容には全く同意できないが、その行動自体にわずかな感謝の念すら抱いている。
全く今の日本のゲイは、平和ボケなのである。
脳味噌まで筋肉質な体育会系の男性や、
ネット上で人種差別的な発言を繰り返す愚かな輩の中には、
ゲイに対する露骨な拒否感を示す人もいる。
しかし女性や若い世代の男性は、ゲイに対して概ね好意的である。
東京や大阪などの大都市には、ゲイ同士が出会える場所が数多いうえに、
ネット上にも男女間よりずっと安全な出会いシステムが用意され、
全国レベルでの浸透を見せている。
「ゲイは出会いが少ないし、差別されていて可哀想」なんて、とんでもない。
みんなそれほど大きなプレッシャーも感じず、毎日を楽しく、贅沢に生きているのだ。
しかし日本にもゲイ差別はある。
アメリカのようにあからさまで、暴力的な弾圧ではない。
存在を認めてそれを潰しにかかるのではなく、「無視」という方法で黙殺するのだ。
自分とは無縁な問題に関わることを、
極力回避しようとする国民性に、ふさわしいやり方である。
こうした態度が目に見えないところで、
数多くのひずみを生じさせているのは、間違いないだろう。
そして残念ながら当事者のゲイにも、その国民性は十二分に備わっている。
自らのセクシュアリティを明示するより、
可能なところまで隠し通そうとする生き方が、一般的なのだ。
個人的な話になるが、僕は両親から職場の人間にまで、
自らのセクシュアリティをカムアウトしている。
そうした生き方を選ぶことで失ったチャンスも、数多くあることは確かなのだが、
幸か不幸か「仮面をかぶったままの人生に意味はない」と、迷いなく信じられる。
だが同じ生き方を、他のゲイに強要する考えは、とうの昔に捨てた。
また新宿二丁目を中心とするゲイ社会を、
もっと活性化させたいという思いも、かなり前に失った。
僕や志を同じくするゲイが頑張ったところで、
大多数のゲイに檻から出ようとする意思がない限り、虚しい努力にしかならない。
日本のゲイが最優先するのは、同性との恋愛やセックス。
ゲイとしてのアイデンテティ、ライフスタイル確立は二の次である。
だから僕も、色々考えるのはやめてしまった。
例えば「ゲイの婚姻制度を構築する闘争」に一生を捧げるより、
いま享受できるものを享受して、楽しく生きることを選んだのだ。
まとめよう。
今の日本のゲイは、弾圧を受けていない代わりに、明確な実体がない。
消費者層として認知されていないのは、
資本主義社会の中の存在として、致命的でもある。
そうした日本のゲイに、石原慎太郎の発言が冷水のように浴びせかけられたのだ。
何だか僕は「俺に認めさせてみろ」と言われたような気がした。
社会での曖昧な立ち位置に甘んじている
日本のゲイに向けた、挑発のようにも感じられたのだ。
矛盾する話だが、バラバラだったマイノリティがひとつにまとまり、
権利を主張していくためには、「仮想敵」の存在が必要不可欠である。
それはこの『ハーヴェイ・ミルク』を見れば、はっきりとわかる。
宗教や道徳を盾に、
あらゆる方向からマイノリティを弾圧しようとする社会や政治家があってはじめて、
抑圧を原動力とした、抵抗の大きなうねりが生まれていく。
僕には資格がないのかもしれないが、鑑賞中何度も涙が溢れ出て止まらなかった。
この場所に参加して、史上初のオープンゲイ政治家、
ハーヴェイの力になれたなら、どんなによかっただろうと思った。
そしてふと石原慎太郎が、日本のゲイに対して「仮想敵」としての役割を
引き受けたがっているように思えてきたのだ。
実は彼のゲイに対するアンチ発言は、これまでにも枚挙の暇がない。
黙殺すれば済むものに、なぜ執拗に絡むのか、不思議に感じられるほどなのだ。
彼自身の2人の息子や、国民的人気を誇った俳優の弟がゲイであるという噂は、
公然の事実のように根強く存在している。
もしかしたら、石原慎太郎が抱くゲイへの深い愛憎は、
我々の想像をはるかに凌駕しているのかもしれない。
製作年:1984年
製作国:アメリカ
監督:ロバート・エプスタイン
________________________
先日、東京都知事の石原慎太郎があからさまなゲイ差別発言をしたことが、
ネットニュースで配信された。
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20101208ddm041010103000c.html
これを受け、怒りを表明するゲイの発言が、これまたネット上に数多く噴出した。
一般のゲイ・ピープルによる憤怒を、数多く目にする機会があったのは、
僕自身がゲイだから。
SNSなどで繋がっている人たちの大半をゲイ・ピープルが占めているため、
彼らの生の声を、他の人よりも多く目にすることができたというわけだ。
なんて客観的態度を見せびらかしていると、
「じゃあアンタはどう思っているんだ」と問い質されそうなので、率直に言おう。
僕は「よくぞ言ってくれたなぁ」と感心している。
発言内容には全く同意できないが、その行動自体にわずかな感謝の念すら抱いている。
全く今の日本のゲイは、平和ボケなのである。
脳味噌まで筋肉質な体育会系の男性や、
ネット上で人種差別的な発言を繰り返す愚かな輩の中には、
ゲイに対する露骨な拒否感を示す人もいる。
しかし女性や若い世代の男性は、ゲイに対して概ね好意的である。
東京や大阪などの大都市には、ゲイ同士が出会える場所が数多いうえに、
ネット上にも男女間よりずっと安全な出会いシステムが用意され、
全国レベルでの浸透を見せている。
「ゲイは出会いが少ないし、差別されていて可哀想」なんて、とんでもない。
みんなそれほど大きなプレッシャーも感じず、毎日を楽しく、贅沢に生きているのだ。
しかし日本にもゲイ差別はある。
アメリカのようにあからさまで、暴力的な弾圧ではない。
存在を認めてそれを潰しにかかるのではなく、「無視」という方法で黙殺するのだ。
自分とは無縁な問題に関わることを、
極力回避しようとする国民性に、ふさわしいやり方である。
こうした態度が目に見えないところで、
数多くのひずみを生じさせているのは、間違いないだろう。
そして残念ながら当事者のゲイにも、その国民性は十二分に備わっている。
自らのセクシュアリティを明示するより、
可能なところまで隠し通そうとする生き方が、一般的なのだ。
個人的な話になるが、僕は両親から職場の人間にまで、
自らのセクシュアリティをカムアウトしている。
そうした生き方を選ぶことで失ったチャンスも、数多くあることは確かなのだが、
幸か不幸か「仮面をかぶったままの人生に意味はない」と、迷いなく信じられる。
だが同じ生き方を、他のゲイに強要する考えは、とうの昔に捨てた。
また新宿二丁目を中心とするゲイ社会を、
もっと活性化させたいという思いも、かなり前に失った。
僕や志を同じくするゲイが頑張ったところで、
大多数のゲイに檻から出ようとする意思がない限り、虚しい努力にしかならない。
日本のゲイが最優先するのは、同性との恋愛やセックス。
ゲイとしてのアイデンテティ、ライフスタイル確立は二の次である。
だから僕も、色々考えるのはやめてしまった。
例えば「ゲイの婚姻制度を構築する闘争」に一生を捧げるより、
いま享受できるものを享受して、楽しく生きることを選んだのだ。
まとめよう。
今の日本のゲイは、弾圧を受けていない代わりに、明確な実体がない。
消費者層として認知されていないのは、
資本主義社会の中の存在として、致命的でもある。
そうした日本のゲイに、石原慎太郎の発言が冷水のように浴びせかけられたのだ。
何だか僕は「俺に認めさせてみろ」と言われたような気がした。
社会での曖昧な立ち位置に甘んじている
日本のゲイに向けた、挑発のようにも感じられたのだ。
矛盾する話だが、バラバラだったマイノリティがひとつにまとまり、
権利を主張していくためには、「仮想敵」の存在が必要不可欠である。
それはこの『ハーヴェイ・ミルク』を見れば、はっきりとわかる。
宗教や道徳を盾に、
あらゆる方向からマイノリティを弾圧しようとする社会や政治家があってはじめて、
抑圧を原動力とした、抵抗の大きなうねりが生まれていく。
僕には資格がないのかもしれないが、鑑賞中何度も涙が溢れ出て止まらなかった。
この場所に参加して、史上初のオープンゲイ政治家、
ハーヴェイの力になれたなら、どんなによかっただろうと思った。
そしてふと石原慎太郎が、日本のゲイに対して「仮想敵」としての役割を
引き受けたがっているように思えてきたのだ。
実は彼のゲイに対するアンチ発言は、これまでにも枚挙の暇がない。
黙殺すれば済むものに、なぜ執拗に絡むのか、不思議に感じられるほどなのだ。
彼自身の2人の息子や、国民的人気を誇った俳優の弟がゲイであるという噂は、
公然の事実のように根強く存在している。
もしかしたら、石原慎太郎が抱くゲイへの深い愛憎は、
我々の想像をはるかに凌駕しているのかもしれない。
原題:PURPLE RAIN
製作年:1984年
製作国:アメリカ
監督:アルバート・マグノーリ
出演:プリンス、アポロニア・コテロ、モリス・デイ

_________________
最近は新作を出しても殆ど話題にならないプリンス。
80年代は、死んでから途方もなく再評価されているマイケル、そしてマドンナとで、
アメリカンポップス界の人気を3分していた。
所詮アイドル映画なので、内容はとやかくいう以前の問題。
鑑賞は主に個人的な理由からだ。
プリンスの魅力って、わかるようでわからないのである。
僕は無類のポップ・ミュージック好きなのだが、
近年遅まきながら、ソウル・ミュージックを楽しめるようになり、
また世界がグッと広がった。以前は苦手だったのである。
しかしプリンスはソウル史全体の中でも、特異な存在感を放っている。
ソウルミュージックの基本を、メキシカン・タコスの味に例えると
(おかしな例えである。あくまで僕の感覚での例えと思っていただければ幸い)、
プリンスの音楽は、その上に生クリームを乗せてきたような
違和を感じさせることがあって、非常に理解しにくいのだ。
またもうひとつ理由がある。
これも個人的なことなのだが、僕は男性ヴォーカルが苦手という偏聴癖の持主なのだ。
そこで「音はプリンスが作っていて、ヴォーカルが女性という体裁のものはないかしら」
と探してみた。
するとあるんですね、シーラEとか、
本作に出演しているアポロニア率いるアポロニア6とか。
チャカ・カーンの名曲『Feel 4 you』なんかもプリンスの作品だし、
比較的新しめのところではモニー・ラブの『BORN 2 B.R.E.E.D.』にも絡んでいる。
ペイズリー・パーク絡みも含むとすれば、元ミッシング・パーソンズのデイルのソロにも
プリンスサウンドの片鱗は感じられる(かなり薄味なんだけど)。
ここらへんは好き、っていうかかなりイイ!
これで少なくとも「プリンスが作る音は好き」ということはわかった。
そしてこの映画を観賞するに至り、もうひとつ理解できたことがある。
プリンスが非常にチャーミングな男である、という事実。
思ったより全然小柄であった。
幼少の頃マリリン・モンローの写真をみて「女装?」と思ったことがあるのだが、
写真には実在のスケールを飛び越えて、嘘を突き通す力がある。
見る者を圧倒するような、肥大化したイメージを提示することが可能なのだ。
アメリカに住んでいれば日常的に歌い踊るプリンスの姿を
目にすることもできたはずだが、
日本だとファンでない限り、
写真を見るだけでもうお腹いっぱいになるようないでたちである。
しかし出っ張った頬骨、モジャモジャしたもみあげが
どアップになったクローズショットだけで彼の魅力を判断したのは、大きな誤りであった。
加えてこの映画でも充分に堪能できる、ステージ上でのショーマンシップの高さ。
ライブで毎回あんなテンションだったら、人気が出て当たり前だ。
この映画のサントラ的な役割も果たしている大ヒットアルバム『パープルレイン』は、
かなり大衆向けということもあり、僕も所有しているが、
いま一度他の作品にもトライしてみようと思う次第であった。
余談だが、前述のアポロニア6はかなり好き。
コルセット姿で男を挑発するというアプローチで
キワモノ路線をひた走ったグループだ。
プロデュースはもちろん、プリンス。

現在のR&B界でもこうしたビアッチ路線は健在だが、
当時はまだまだ「やらされている」感が濃厚に漂っており、公開SMぽくて笑える。
実は前身にヴァニティ6というガールグループがあり、
フロントのヴァニティは本作でプリンスの相手役を務める予定だったのだが、
撮影中に降板したらしい。
トップレスシーンがあるので、いい加減堪えられなくなったのかも……。
ヴァニティ→アポロニアとフロントは替わったのだが、
バックの2人はそのままというグループ構成にも、一抹の哀愁が漂っている。
しかしこの2人が、結構キャラ立ちしているのだ。
”スーザン”がロリータ路線で、
”ブレンダ”が哀しいほどの蓮っ葉路線。
ソウル界ではその後もアン・ヴォーグからデスチャまで様々な
ガールグループが登場したが、
ブレンダのようなスポイルキャラは、類を見ない。
本作でもクチャクチャガムを噛みながら歌い踊るブレンダの勇姿(?)が
確認できるので、物好きな方はチェックしてみて欲しい。
製作年:1984年
製作国:アメリカ
監督:アルバート・マグノーリ
出演:プリンス、アポロニア・コテロ、モリス・デイ
_________________
最近は新作を出しても殆ど話題にならないプリンス。
80年代は、死んでから途方もなく再評価されているマイケル、そしてマドンナとで、
アメリカンポップス界の人気を3分していた。
所詮アイドル映画なので、内容はとやかくいう以前の問題。
鑑賞は主に個人的な理由からだ。
プリンスの魅力って、わかるようでわからないのである。
僕は無類のポップ・ミュージック好きなのだが、
近年遅まきながら、ソウル・ミュージックを楽しめるようになり、
また世界がグッと広がった。以前は苦手だったのである。
しかしプリンスはソウル史全体の中でも、特異な存在感を放っている。
ソウルミュージックの基本を、メキシカン・タコスの味に例えると
(おかしな例えである。あくまで僕の感覚での例えと思っていただければ幸い)、
プリンスの音楽は、その上に生クリームを乗せてきたような
違和を感じさせることがあって、非常に理解しにくいのだ。
またもうひとつ理由がある。
これも個人的なことなのだが、僕は男性ヴォーカルが苦手という偏聴癖の持主なのだ。
そこで「音はプリンスが作っていて、ヴォーカルが女性という体裁のものはないかしら」
と探してみた。
するとあるんですね、シーラEとか、
本作に出演しているアポロニア率いるアポロニア6とか。
チャカ・カーンの名曲『Feel 4 you』なんかもプリンスの作品だし、
比較的新しめのところではモニー・ラブの『BORN 2 B.R.E.E.D.』にも絡んでいる。
ペイズリー・パーク絡みも含むとすれば、元ミッシング・パーソンズのデイルのソロにも
プリンスサウンドの片鱗は感じられる(かなり薄味なんだけど)。
ここらへんは好き、っていうかかなりイイ!
これで少なくとも「プリンスが作る音は好き」ということはわかった。
そしてこの映画を観賞するに至り、もうひとつ理解できたことがある。
プリンスが非常にチャーミングな男である、という事実。
思ったより全然小柄であった。
幼少の頃マリリン・モンローの写真をみて「女装?」と思ったことがあるのだが、
写真には実在のスケールを飛び越えて、嘘を突き通す力がある。
見る者を圧倒するような、肥大化したイメージを提示することが可能なのだ。
アメリカに住んでいれば日常的に歌い踊るプリンスの姿を
目にすることもできたはずだが、
日本だとファンでない限り、
写真を見るだけでもうお腹いっぱいになるようないでたちである。
しかし出っ張った頬骨、モジャモジャしたもみあげが
どアップになったクローズショットだけで彼の魅力を判断したのは、大きな誤りであった。
加えてこの映画でも充分に堪能できる、ステージ上でのショーマンシップの高さ。
ライブで毎回あんなテンションだったら、人気が出て当たり前だ。
この映画のサントラ的な役割も果たしている大ヒットアルバム『パープルレイン』は、
かなり大衆向けということもあり、僕も所有しているが、
いま一度他の作品にもトライしてみようと思う次第であった。
余談だが、前述のアポロニア6はかなり好き。
コルセット姿で男を挑発するというアプローチで
キワモノ路線をひた走ったグループだ。
プロデュースはもちろん、プリンス。
現在のR&B界でもこうしたビアッチ路線は健在だが、
当時はまだまだ「やらされている」感が濃厚に漂っており、公開SMぽくて笑える。
実は前身にヴァニティ6というガールグループがあり、
フロントのヴァニティは本作でプリンスの相手役を務める予定だったのだが、
撮影中に降板したらしい。
トップレスシーンがあるので、いい加減堪えられなくなったのかも……。
ヴァニティ→アポロニアとフロントは替わったのだが、
バックの2人はそのままというグループ構成にも、一抹の哀愁が漂っている。
しかしこの2人が、結構キャラ立ちしているのだ。
”スーザン”がロリータ路線で、
”ブレンダ”が哀しいほどの蓮っ葉路線。
ソウル界ではその後もアン・ヴォーグからデスチャまで様々な
ガールグループが登場したが、
ブレンダのようなスポイルキャラは、類を見ない。
本作でもクチャクチャガムを噛みながら歌い踊るブレンダの勇姿(?)が
確認できるので、物好きな方はチェックしてみて欲しい。
原題:Pauline à la plage
製作年:1983年
製作国:フランス
監督/脚本:エリック・ロメール
出演:アリエル・ドンバール、パスカル・グレゴリー、
フェオドール・アドキン、アマンダ・ラングレ

________________________
今年の初めに亡くなった、エリック・ロメール監督の作品。
彼の作品を観るのはこれが初めてだが、
ヌーヴェルバーグの時代に台頭した監督のひとりらしい。
とはいえ、この作品が撮影されたのは80年代だし、
それ以降もコンスタントに映画を撮っていたということは、
安定した実力と人気を誇った監督だったのだろう。
こちらも、大げさなところは少しもないのに、非常に面白い作品だった。
テーマはズバリ「恋愛」。
「愛したい」女性と「愛されたい」男性と、
そのどちらにも食傷気味なのに、来る者は拒めない男性との間に生まれた
トライアングルな関係を軸に、ストーリーは展開していく。
相手を思いやる気持ちはありつつも、それぞれがエゴを存分に発揮し、
自分の意見を徹頭徹尾に口にしていくので、
コトはどんどん複雑になっていく。
口を挟んだら馬に蹴られそうな「人の恋路」を、
淡々とリアルに喜劇化しているので、
パリゴ達は鑑賞後、それぞれの恋愛観を披歴し合い、
議論に花を咲かせたに違いない。
現代にも通ずるシニシズムはしっかりと持ち合わせながら、
最終的に女性へやさしい視線を投げかけているのも、印象的だった。
また、ヒロインのひとりであるアリエル・ドンバールがすごくいい。
個人的には最近、歌手としての彼女がマイブームで、
アルバムをすべて揃えようという勢いなのだが、2010年現在で、御年は52歳。
美しいだけでなく、どこか妖怪じみたエロチシズムを漂わせているところが
素敵な女性だ。
この映画に出演した頃はまだ30代で、今よりもっと健康的な雰囲気だが、
それにしても、エキセントリックな灰汁だけはどうにも抜けきらない感じ。
そんな女性が、恋愛という普遍的な命題を前に手を焼いている感じがなんとも滑稽で、
ともすれば単調に陥りそうな場面の連続を、刺激的に見せてくれる。
特にまだ禿げていないパスカル・グレゴリーとのやり取りがおかしくて、
何度も高笑いしてしまった。特におかしい場面でもないはずなのにね。
ロメール監督との絡み以外では、いまひとつ作品に恵まれていないようだが、
女優としての彼女も大いに気になっているので、
これからどんどんチェックしていこうっと。
製作年:1983年
製作国:フランス
監督/脚本:エリック・ロメール
出演:アリエル・ドンバール、パスカル・グレゴリー、
フェオドール・アドキン、アマンダ・ラングレ
________________________
今年の初めに亡くなった、エリック・ロメール監督の作品。
彼の作品を観るのはこれが初めてだが、
ヌーヴェルバーグの時代に台頭した監督のひとりらしい。
とはいえ、この作品が撮影されたのは80年代だし、
それ以降もコンスタントに映画を撮っていたということは、
安定した実力と人気を誇った監督だったのだろう。
こちらも、大げさなところは少しもないのに、非常に面白い作品だった。
テーマはズバリ「恋愛」。
「愛したい」女性と「愛されたい」男性と、
そのどちらにも食傷気味なのに、来る者は拒めない男性との間に生まれた
トライアングルな関係を軸に、ストーリーは展開していく。
相手を思いやる気持ちはありつつも、それぞれがエゴを存分に発揮し、
自分の意見を徹頭徹尾に口にしていくので、
コトはどんどん複雑になっていく。
口を挟んだら馬に蹴られそうな「人の恋路」を、
淡々とリアルに喜劇化しているので、
パリゴ達は鑑賞後、それぞれの恋愛観を披歴し合い、
議論に花を咲かせたに違いない。
現代にも通ずるシニシズムはしっかりと持ち合わせながら、
最終的に女性へやさしい視線を投げかけているのも、印象的だった。
また、ヒロインのひとりであるアリエル・ドンバールがすごくいい。
個人的には最近、歌手としての彼女がマイブームで、
アルバムをすべて揃えようという勢いなのだが、2010年現在で、御年は52歳。
美しいだけでなく、どこか妖怪じみたエロチシズムを漂わせているところが
素敵な女性だ。
この映画に出演した頃はまだ30代で、今よりもっと健康的な雰囲気だが、
それにしても、エキセントリックな灰汁だけはどうにも抜けきらない感じ。
そんな女性が、恋愛という普遍的な命題を前に手を焼いている感じがなんとも滑稽で、
ともすれば単調に陥りそうな場面の連続を、刺激的に見せてくれる。
特にまだ禿げていないパスカル・グレゴリーとのやり取りがおかしくて、
何度も高笑いしてしまった。特におかしい場面でもないはずなのにね。
ロメール監督との絡み以外では、いまひとつ作品に恵まれていないようだが、
女優としての彼女も大いに気になっているので、
これからどんどんチェックしていこうっと。
原題:MATADOR
製作年:1986年
製作国:スペイン
監督:ペドロ・アルモドバル
出演:アサンプタ・セルナ、アントニオ・バンデラス、
ナチョ・マルティネス、エヴァ・コーボ、
フリエタ・セラーノ、ビビ・アンデショーン

_________________
最新作が日本でも公開中のペドロ・アルモドバル監督。
そちらの方はまだ未見なのだが、
「早く出なきゃ」とせわしなくしていたツタヤで
パッと手に取った旧作を鑑賞した。
「まだ観ていないの、あったんだ」と思いつつ...。
近年の彼の作品は、本人の成熟もあって、
より深いタッチのヒューマニズムに流れているが、
80年代はフェティッシュなセックスにテーマを置いた作品が多く、
またそれほど名が売れていなかったこともあって、
好き放題やっている感じが楽しい。
『セクシリア』のクソチビリシーンなんか、涙が出るほど笑った。
本作は、B級ホラー映画のイメージを借りてきた冒頭こそ貧乏臭いが、
これはもちろん計算されたもので(またはオマージュ)、
監督の「これで大真面目に1本撮るぞ」という姿勢に
どんどん引き込まれる。
90年代に世界中で大ヒットした『アタメ』などの
諸作品につながる作風が、この時点ですでに確立されているのだ。
劇中で失恋に涙する娘に向かい、
母親が「愛は永遠に続かないわ」と諭すシーンがあるが、
離婚が当たり前となった現代において、
愛の頂点でお互いを殺め合う関係を、
ひとつの「究極のかたち」としても、差し支えはないはず。
それが映画の中であればなおさらで、
世の常識を根底から覆すような美意識が
積極的に肯定されているのが、痛快な限り。
また個々のキャラクターが持つ骨太なパーソナリティは南欧独特で、
非常にエキゾチズムがそそられる。
それは女性において特に顕著で、
弁護士と被告の母親の、お互い言いたい放題なやりとりには、
思わず高笑い。
無理に笑わせる必要のないはずの場面で笑えると、
何か得をしたような気分になり、
「やっぱスペイン映画っていいわ~」と思ってしまう。
はじめは貧乏臭いがだんだん魅力的に見えてくる
バンデラスも頑張っていたが、
彼がなぜ「先生」に献身を捧げたのかの描き方だけは、
ちょっと雑だったかもしれない。
また闘牛士候補生のジャージの股間を執拗に追う
クローズショットがあったのだが、あれは誰の視点?
刑事が実はゲイだったのかしらん。
製作年:1986年
製作国:スペイン
監督:ペドロ・アルモドバル
出演:アサンプタ・セルナ、アントニオ・バンデラス、
ナチョ・マルティネス、エヴァ・コーボ、
フリエタ・セラーノ、ビビ・アンデショーン
_________________
最新作が日本でも公開中のペドロ・アルモドバル監督。
そちらの方はまだ未見なのだが、
「早く出なきゃ」とせわしなくしていたツタヤで
パッと手に取った旧作を鑑賞した。
「まだ観ていないの、あったんだ」と思いつつ...。
近年の彼の作品は、本人の成熟もあって、
より深いタッチのヒューマニズムに流れているが、
80年代はフェティッシュなセックスにテーマを置いた作品が多く、
またそれほど名が売れていなかったこともあって、
好き放題やっている感じが楽しい。
『セクシリア』のクソチビリシーンなんか、涙が出るほど笑った。
本作は、B級ホラー映画のイメージを借りてきた冒頭こそ貧乏臭いが、
これはもちろん計算されたもので(またはオマージュ)、
監督の「これで大真面目に1本撮るぞ」という姿勢に
どんどん引き込まれる。
90年代に世界中で大ヒットした『アタメ』などの
諸作品につながる作風が、この時点ですでに確立されているのだ。
劇中で失恋に涙する娘に向かい、
母親が「愛は永遠に続かないわ」と諭すシーンがあるが、
離婚が当たり前となった現代において、
愛の頂点でお互いを殺め合う関係を、
ひとつの「究極のかたち」としても、差し支えはないはず。
それが映画の中であればなおさらで、
世の常識を根底から覆すような美意識が
積極的に肯定されているのが、痛快な限り。
また個々のキャラクターが持つ骨太なパーソナリティは南欧独特で、
非常にエキゾチズムがそそられる。
それは女性において特に顕著で、
弁護士と被告の母親の、お互い言いたい放題なやりとりには、
思わず高笑い。
無理に笑わせる必要のないはずの場面で笑えると、
何か得をしたような気分になり、
「やっぱスペイン映画っていいわ~」と思ってしまう。
はじめは貧乏臭いがだんだん魅力的に見えてくる
バンデラスも頑張っていたが、
彼がなぜ「先生」に献身を捧げたのかの描き方だけは、
ちょっと雑だったかもしれない。
また闘牛士候補生のジャージの股間を執拗に追う
クローズショットがあったのだが、あれは誰の視点?
刑事が実はゲイだったのかしらん。

