カレンダー
| 01 | 2026/02 | 03 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
カテゴリー
こんな映画も、レビューしてます★
最新コメント
最新記事
(08/18)
(03/10)
(07/28)
(04/13)
(04/10)
最新トラックバック
プロフィール
HN:
lulabox
性別:
男性
自己紹介:
30代の編集者/ライター。ゲイ。映画、音楽大好きですが、仕事では書く機会がなく...。ので、こちらでは趣味全開にしちゃいます。
popdorianz@yahoo.co.jp
popdorianz@yahoo.co.jp
ブログ内検索
P R
カウンター
映画はエンターテインメントでありつつも、アートフォームであって欲しいと願っています。 同じような気持ちで映画を観ているひとの慰みになれば幸いです★
原題:TO DIE FOR
製作年:1995年
製作国:アメリカ
監督:ガス・ヴァン・サント
出演:二コール・キッドマン、マット・ディロン、
ケイシー・アフレック、ホアキン・フェニックス、イリーナ・ダグラス

_____________________________
人は皆「テレビに出たい」と思うのだろうか。
漠然とした願望も含めると、ほとんどがそう願うものなのかもしれない。
しかし、自分の望まないかたちを強いられてまで
テレビに出なければならないとすれば、
大半の人々はその願いを取り下げようとするだろう。
僕は仕事で、紙やウェブ媒体の制作を行っている。
この仕事では、各ページを制作するにあたり、
情報を統一するための「テーマ」なり「切り口」なりが求められる。
そのうえで紹介する情報を選別し、取材へと至るわけだが、
進行上で”ページテーマからのズレ”が生じることも数多い。
企画の趣旨をあらかじめ説明したにも関わらず、
いざ取材、の段階で小さな狂いが生じることは、多々あるのだ。
しかし紙やウェブ媒体の制作には、
先方校正という作業が必ず組み込まれている
(ゴシップ誌などを除く。またこの作業が必須となったのは、ここ25年ぐらいのこと)、
このため最終的な仕上がりにおいて、取材する側とされる側に、
甚だしい見解の相違が生じることは少ない。
ところがテレビ番組の制作上には、先方校正という作業がないのである。
つまり一度出演を承諾して、撮影されたが最後、
あとはどのように編集、放送されても文句を言えないわけだ。
この事実が即、非人道的な情報操作に繋がるわけではないのだが、
考えようによっては、とても恐しいことである。
マスメディアという括りでは同業者にあたるのかもしれないが、
僕にはとてもできない仕事だ。
権力が大きい分、責任も重過ぎるのである。
感覚の一部が麻痺している人間でなければ、
テレビのディレクターなんて勤まらない、と本気で思う。
少し話が変わるが、僕の友人から、3人ほどテレビに出る人間が生まれた。
Aは今やマスメディアの寵児で、引っ張りだこの人気者。
Bはもって今年いっぱいだろうというのが、内輪だけでなく世間一般の評価である。
Cはちょくちょくテレビに顔を出しているものの、ほぼ無名に等しい。
しかしいざテレビに出るとなって、
言動に最も大きな変化を生じさせたのはCであった。
「有名人の●●さんとご飯を食べに行った」などと吹聴して回るのは可愛い方で、
交際費やタクシー代に尋常でない額を使うようになった。
こうした病に浮かされていると、友人の忠告など一切耳に入らなくなるものらしい。
Cはそうした浪費が自分の将来のためになる、と
無邪気に信じ込んでいる様子であった。
たぶん誰かにそう吹き込まれたのだろう。
またCは、素人とともに出演する番組へDを引き込んだ。
説得の文句は「テレビに出られるんだよ」だったそうだ。
Dは何度かその番組に出演したのち、Cの誘いを断るようになった。
Cは「どうして? テレビに出られるんだよ」と繰り返したそうだが、
Dは「だから何?」と考えたようだ。
世の中の一部の人間にとって、テレビに出ることは人生の目的そのものになるようだ。
そこで何をするのかではなく、テレビに出ること自体に意味を見出すのである。
例え自分の予想に反する編集がなされても、大した失望には至らないらしい。
この映画は、テレビの魔力に取り憑かれた人間の、
浅薄な心理や行動を題材にしたサスペンスである。
非常にシニカルな脚本で、ときにコメディを観ているようにも感じられたが、
実際の事件をベースとしているところが、笑えない。
こんな女、身の周りにいたら、さぞかし迷惑だろう……。
しかし日本ですら先述の有様なのだから、
アメリカにはこうした人間がウヨウヨしているに違いない。
行動力や積極性はひと一倍あるのだから、
正しい方向に使えば成功できそうなものだが、
スタート時点で目的そのものを見誤っているのである。
なぜそうなってしまうのだろうか? 答えは簡単。
「そこに思想がない」からである。
しかし二コール・キッドマンの演技は見事だった。
悪女と呼ぶにはちょっとオツムが足りなすぎる役柄だが、
まず喋り方そのものが、他作で観た彼女と随分違う。
軽薄そのものを絵に描いたような成り切りぶりが、憑依のレベルに達しているのである。
自分の中にも当然潜んでいるはずの自己顕示欲を、
拡大表現してみせたのだろう。
女優としてのイメージそのものが固定される危険もあったはずだが、
その後の活躍ぶりを見ると、上手にやり過ごしたようである。
製作年:1995年
製作国:アメリカ
監督:ガス・ヴァン・サント
出演:二コール・キッドマン、マット・ディロン、
ケイシー・アフレック、ホアキン・フェニックス、イリーナ・ダグラス
_____________________________
人は皆「テレビに出たい」と思うのだろうか。
漠然とした願望も含めると、ほとんどがそう願うものなのかもしれない。
しかし、自分の望まないかたちを強いられてまで
テレビに出なければならないとすれば、
大半の人々はその願いを取り下げようとするだろう。
僕は仕事で、紙やウェブ媒体の制作を行っている。
この仕事では、各ページを制作するにあたり、
情報を統一するための「テーマ」なり「切り口」なりが求められる。
そのうえで紹介する情報を選別し、取材へと至るわけだが、
進行上で”ページテーマからのズレ”が生じることも数多い。
企画の趣旨をあらかじめ説明したにも関わらず、
いざ取材、の段階で小さな狂いが生じることは、多々あるのだ。
しかし紙やウェブ媒体の制作には、
先方校正という作業が必ず組み込まれている
(ゴシップ誌などを除く。またこの作業が必須となったのは、ここ25年ぐらいのこと)、
このため最終的な仕上がりにおいて、取材する側とされる側に、
甚だしい見解の相違が生じることは少ない。
ところがテレビ番組の制作上には、先方校正という作業がないのである。
つまり一度出演を承諾して、撮影されたが最後、
あとはどのように編集、放送されても文句を言えないわけだ。
この事実が即、非人道的な情報操作に繋がるわけではないのだが、
考えようによっては、とても恐しいことである。
マスメディアという括りでは同業者にあたるのかもしれないが、
僕にはとてもできない仕事だ。
権力が大きい分、責任も重過ぎるのである。
感覚の一部が麻痺している人間でなければ、
テレビのディレクターなんて勤まらない、と本気で思う。
少し話が変わるが、僕の友人から、3人ほどテレビに出る人間が生まれた。
Aは今やマスメディアの寵児で、引っ張りだこの人気者。
Bはもって今年いっぱいだろうというのが、内輪だけでなく世間一般の評価である。
Cはちょくちょくテレビに顔を出しているものの、ほぼ無名に等しい。
しかしいざテレビに出るとなって、
言動に最も大きな変化を生じさせたのはCであった。
「有名人の●●さんとご飯を食べに行った」などと吹聴して回るのは可愛い方で、
交際費やタクシー代に尋常でない額を使うようになった。
こうした病に浮かされていると、友人の忠告など一切耳に入らなくなるものらしい。
Cはそうした浪費が自分の将来のためになる、と
無邪気に信じ込んでいる様子であった。
たぶん誰かにそう吹き込まれたのだろう。
またCは、素人とともに出演する番組へDを引き込んだ。
説得の文句は「テレビに出られるんだよ」だったそうだ。
Dは何度かその番組に出演したのち、Cの誘いを断るようになった。
Cは「どうして? テレビに出られるんだよ」と繰り返したそうだが、
Dは「だから何?」と考えたようだ。
世の中の一部の人間にとって、テレビに出ることは人生の目的そのものになるようだ。
そこで何をするのかではなく、テレビに出ること自体に意味を見出すのである。
例え自分の予想に反する編集がなされても、大した失望には至らないらしい。
この映画は、テレビの魔力に取り憑かれた人間の、
浅薄な心理や行動を題材にしたサスペンスである。
非常にシニカルな脚本で、ときにコメディを観ているようにも感じられたが、
実際の事件をベースとしているところが、笑えない。
こんな女、身の周りにいたら、さぞかし迷惑だろう……。
しかし日本ですら先述の有様なのだから、
アメリカにはこうした人間がウヨウヨしているに違いない。
行動力や積極性はひと一倍あるのだから、
正しい方向に使えば成功できそうなものだが、
スタート時点で目的そのものを見誤っているのである。
なぜそうなってしまうのだろうか? 答えは簡単。
「そこに思想がない」からである。
しかし二コール・キッドマンの演技は見事だった。
悪女と呼ぶにはちょっとオツムが足りなすぎる役柄だが、
まず喋り方そのものが、他作で観た彼女と随分違う。
軽薄そのものを絵に描いたような成り切りぶりが、憑依のレベルに達しているのである。
自分の中にも当然潜んでいるはずの自己顕示欲を、
拡大表現してみせたのだろう。
女優としてのイメージそのものが固定される危険もあったはずだが、
その後の活躍ぶりを見ると、上手にやり過ごしたようである。
PR
原題:EYES WIDE SHUT
製作年:1999年
製作国:アメリカ/イギリス
監督:スタンリー・キューブリック
出演:トム・クルーズ、二コール・キッドマン、
シドニー・ポラック、マリー・リチャードソン
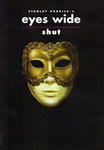
________________________
唐突だが、僕が最も好きな映画は、
アンジェイ・ズラウスキ監督、
イザベル・アジャーニ主演の『ポゼッション』である。
夫が持つ”秘密”に懊悩するあまり、
自らも醜悪な”秘密”を作ってしまう女の業を、
極端に描き切った傑作なのだが、
本作の主題は、この映画とよく似ていた。
ただし本作で懊悩するのは男のほう。
妻の心理的な姦淫と、その告白にショックを受け、
自らも”秘密”を作るべく、夜の街をさまよい始める。
健康的なアメリカン・エリート役によくはまるトム・クルーズが、
捨てられた仔犬のように傷つき、
セックスをめぐる冒険へと足を踏み入れていくサマを眺めていたら、
サディスティックな歓びがフツフツと湧き上がってきた。
ここまでは楽しかったのだが……。
本作のハイライトは、豪華絢爛な乱交パーティのシーン。
不気味かつ重厚な映像には一見の価値がある。
しかし物語はその後、
なぜかつまらない謎解きに拘る犯罪劇のようなベクトルに向かってしまう。
何てもったいないのだろう!
これでは、中途半端に古風なラブストーリーではないか。
キューブリックは一体なぜ、
あの洋館でトム・クルーズに全裸を曝させなかったのだろうか
(逆に二コール・キッドマンのヌードは、作品中大した意味もなく、
執拗にカット・インされる)?
実現したら、映画史上でもかなりセクシーな名場面として、
人々の記憶に残ったに違いない。
こうした演出上の手加減や、俳優自身の覚悟不足が積み重なり、
作品全体の質が下がってしまった感は、否めない。
やはりトム・クルーズのような能天気俳優は、
キューブリックと組んでも、この程度なんだなぁ……
(その点『ドッグヴィル』でレイプされまくる女を演じた
二コール・キッドマンの役者魂は、かなり立派である)。
そういえばデイヴィット・リンチ監督の
『ツイン・ピークス ローラ・パーマー最期の7日間』も、
堕落した女子高生の”秘密”が物語の鍵となる作品だった。
キリスト教的なオチには肩透かしを食らったが、
一貫しておどろおどろしい演出の印象がすべてを凌駕し、
濃厚なリンチワールドに酔い痴れたものだ。
このテのテーマは最も好きなので、つい評価が厳しくなってしまう。
遺作なだけに、キューブリックにもその底力を見せつけて欲しかった。
製作年:1999年
製作国:アメリカ/イギリス
監督:スタンリー・キューブリック
出演:トム・クルーズ、二コール・キッドマン、
シドニー・ポラック、マリー・リチャードソン
________________________
唐突だが、僕が最も好きな映画は、
アンジェイ・ズラウスキ監督、
イザベル・アジャーニ主演の『ポゼッション』である。
夫が持つ”秘密”に懊悩するあまり、
自らも醜悪な”秘密”を作ってしまう女の業を、
極端に描き切った傑作なのだが、
本作の主題は、この映画とよく似ていた。
ただし本作で懊悩するのは男のほう。
妻の心理的な姦淫と、その告白にショックを受け、
自らも”秘密”を作るべく、夜の街をさまよい始める。
健康的なアメリカン・エリート役によくはまるトム・クルーズが、
捨てられた仔犬のように傷つき、
セックスをめぐる冒険へと足を踏み入れていくサマを眺めていたら、
サディスティックな歓びがフツフツと湧き上がってきた。
ここまでは楽しかったのだが……。
本作のハイライトは、豪華絢爛な乱交パーティのシーン。
不気味かつ重厚な映像には一見の価値がある。
しかし物語はその後、
なぜかつまらない謎解きに拘る犯罪劇のようなベクトルに向かってしまう。
何てもったいないのだろう!
これでは、中途半端に古風なラブストーリーではないか。
キューブリックは一体なぜ、
あの洋館でトム・クルーズに全裸を曝させなかったのだろうか
(逆に二コール・キッドマンのヌードは、作品中大した意味もなく、
執拗にカット・インされる)?
実現したら、映画史上でもかなりセクシーな名場面として、
人々の記憶に残ったに違いない。
こうした演出上の手加減や、俳優自身の覚悟不足が積み重なり、
作品全体の質が下がってしまった感は、否めない。
やはりトム・クルーズのような能天気俳優は、
キューブリックと組んでも、この程度なんだなぁ……
(その点『ドッグヴィル』でレイプされまくる女を演じた
二コール・キッドマンの役者魂は、かなり立派である)。
そういえばデイヴィット・リンチ監督の
『ツイン・ピークス ローラ・パーマー最期の7日間』も、
堕落した女子高生の”秘密”が物語の鍵となる作品だった。
キリスト教的なオチには肩透かしを食らったが、
一貫しておどろおどろしい演出の印象がすべてを凌駕し、
濃厚なリンチワールドに酔い痴れたものだ。
このテのテーマは最も好きなので、つい評価が厳しくなってしまう。
遺作なだけに、キューブリックにもその底力を見せつけて欲しかった。
製作年:1992年
製作国:日本
監督:田代廣孝
出演:佐野史郎、戸川純、ルビー・モレノ

____________________________
戸川純目当てで観た作品。
80年代の元祖・不思議少女的にシンパサイズするわけではないが、
彼女が個性的な芸人であることは確かなので、大好きだ。
音楽ではソロ作やヤプーズ、そしてゲルニカなどで傑作を発表しているが、
女優業はどうなのか。
あまりチェックしてこなかったので、遅まきながら探し始めた。
彼女の個性を活かしきった代表作ってあるのだろうか?
あればとっくに観ているはずだしなぁ…… 、と思いつつ鑑賞していたが、
残念ながら、本作では助演扱いだった。
彼女自身がトーク番組などでよく語るくだりに
「私は意識して”変わった女”を演じているわけではない」というのがある。
テレビに出られるくらいだから異常というほどではないのだが、
挙動や喋り方に、他者との大きなズレがあるのは確かだ。
おかしなもので、映画の世界でも、カメラの前では「自然な」演技が要求される。
そして戸川純は、このパラドックスにはまってしまう。
「極力自然に」を心がけているはずの演技が、
どこかわざとらしく映ってしまうのである。
もともとが変わっているのだから、しょうがない。
しかし女優としては、大きな欠点として捉えられかねない。
少なくとも、キャスティングを敬遠される理由にはなってしまいそうだ。
共演の佐野史郎はサイコ野郎がはまり役で、揺るぎのない名声を確立しているが、
自然な演技ができる俳優だ。
内部に蠢く狂気を印象づけるには、
一見淡々としている、という側面を巧く表現できると効果的なのかもしれない。
静があるから動が際立つ、ということである。
しかし、それはあくまで手段のひとつ。
初めから終わりまで全開の狂気があったって、いいはずだ。
戸川純のために書き下ろされた脚本が1本くらいあっても、不思議ではなかった。
彼女はそのくらいの器の大きさや、魅力を持った素材で、
活かしきれれば日本の映画史上に残る1本が生まれたはずなのに。
フランスだったらきっと、誰かが何とかしただろうなぁ……、かなり惜しまれる。
映画としてはルビー・モレノの出世作にあたり、
日本人男性のフィリピン人女性に対する、非人道的な行為を軸に展開していく。
日本の田舎に嫁ぎに来た現地妻の次世代が、
逆に日本人を切り捨てていく、という構成は面白いと思った。
近年の若い世代は、ディスカバー・ジャパンをクールと捉えており、
農業や伝統工芸に対する価値観は反転傾向にあるが、
ほんの20年前まで、地方での暮らしに抱かれていたイメージは
陰鬱なものだったということを、本作ではいま一度確認できる。
光を抑えた色や画面づくりはきれいなのだが、
そこにこだわるあまりか何度も同じような場面が続き、
展開がのろいなと感じられる箇所がいくつかあった。
また見苦しい場面ほど長く、ネチネチしているな~と感じないでもなかったが、
そこは好みの分かれるところだろう。
製作国:日本
監督:田代廣孝
出演:佐野史郎、戸川純、ルビー・モレノ
____________________________
戸川純目当てで観た作品。
80年代の元祖・不思議少女的にシンパサイズするわけではないが、
彼女が個性的な芸人であることは確かなので、大好きだ。
音楽ではソロ作やヤプーズ、そしてゲルニカなどで傑作を発表しているが、
女優業はどうなのか。
あまりチェックしてこなかったので、遅まきながら探し始めた。
彼女の個性を活かしきった代表作ってあるのだろうか?
あればとっくに観ているはずだしなぁ…… 、と思いつつ鑑賞していたが、
残念ながら、本作では助演扱いだった。
彼女自身がトーク番組などでよく語るくだりに
「私は意識して”変わった女”を演じているわけではない」というのがある。
テレビに出られるくらいだから異常というほどではないのだが、
挙動や喋り方に、他者との大きなズレがあるのは確かだ。
おかしなもので、映画の世界でも、カメラの前では「自然な」演技が要求される。
そして戸川純は、このパラドックスにはまってしまう。
「極力自然に」を心がけているはずの演技が、
どこかわざとらしく映ってしまうのである。
もともとが変わっているのだから、しょうがない。
しかし女優としては、大きな欠点として捉えられかねない。
少なくとも、キャスティングを敬遠される理由にはなってしまいそうだ。
共演の佐野史郎はサイコ野郎がはまり役で、揺るぎのない名声を確立しているが、
自然な演技ができる俳優だ。
内部に蠢く狂気を印象づけるには、
一見淡々としている、という側面を巧く表現できると効果的なのかもしれない。
静があるから動が際立つ、ということである。
しかし、それはあくまで手段のひとつ。
初めから終わりまで全開の狂気があったって、いいはずだ。
戸川純のために書き下ろされた脚本が1本くらいあっても、不思議ではなかった。
彼女はそのくらいの器の大きさや、魅力を持った素材で、
活かしきれれば日本の映画史上に残る1本が生まれたはずなのに。
フランスだったらきっと、誰かが何とかしただろうなぁ……、かなり惜しまれる。
映画としてはルビー・モレノの出世作にあたり、
日本人男性のフィリピン人女性に対する、非人道的な行為を軸に展開していく。
日本の田舎に嫁ぎに来た現地妻の次世代が、
逆に日本人を切り捨てていく、という構成は面白いと思った。
近年の若い世代は、ディスカバー・ジャパンをクールと捉えており、
農業や伝統工芸に対する価値観は反転傾向にあるが、
ほんの20年前まで、地方での暮らしに抱かれていたイメージは
陰鬱なものだったということを、本作ではいま一度確認できる。
光を抑えた色や画面づくりはきれいなのだが、
そこにこだわるあまりか何度も同じような場面が続き、
展開がのろいなと感じられる箇所がいくつかあった。
また見苦しい場面ほど長く、ネチネチしているな~と感じないでもなかったが、
そこは好みの分かれるところだろう。
原題:Margaret's Museum
製作年:1995年
製作国:イギリス/カナダ
監督:モート・ランセン
出演:ヘレナ・ボナム・カーター、クライヴ・ラッセル、
ケイト・ネリガン、クレイグ・オレジニク、ケネス・ウェルシュ

___________________________
ティム・バートンと結婚する前のヘレナ・ボナム・カーターが、大好き。
本作も、だいぶ前から見ようとは思っていたのだが、
タイトルやパッケージに記されたあらすじを見て、敬遠していた。
B級ぽい匂いがぷんぷんしていたのだ。
~以下 パッケージに記されたあらすじの抜粋~
『脳髄を凍らせる、驚愕のエロティック・サイコ・サスペンス!』
ある事情で男を拒み続けてきたヒロイン、マーガレット
(中略)
彼女はニールとのセックスに溺れる愛欲の女に
(中略)
早過ぎるニールの死によって情念のオンナと化したマーガレットは、
彼の遺体からその男根を切断して...
ホント嘘ばっかり。
本来のあらすじから大きくかけ離れている部分を抜粋したのだが、
マーガレットには、「ある事情」というほど大それたものは、ない。
また描かれているのは新婚夫婦の純粋な生活で、
濡れ場というほどの濡れ場はワンシーンだけ。
最後に、マーガレットが切断したのはニールの男根では、ない。
このビデオを販売しているのはマクザムという会社だが
(現在も続いている会社ですぞ)、
映画ファンをなめているんじゃないかと思う。
陳腐な捏造に騙されて、作品を手に取るバカがいるとでも思っているのかしらん。
嘘をついた方が売れ行きは伸びる、と考えているところが浅はか過ぎて、
思わず冷笑してしまう。
この映画は、エロティック・サイコ・サスペンスでは決してない。
人権を軽んじられながらも家族を愛し、
必死に生き続けようとした人間の姿を描いた、炭鉱哀史だ。
舞台となるカナダ・ノバスコシア州の風景を、
全編に渡って色鮮やかに映し出しており、
鑑賞後には清々しい印象が残るほどである。
終盤のエキセントリックなエピソードが、
物語にスパイスを加えていることは確かだが、
それはあまりに無常な人生に対する、
マーガレットなりの怒り、そして悲しみの表現なのだ。
頑固で、旺盛な反骨精神に忠実なあまり、身を滅ぼしていく女は、
まさにヘレナのはまり役。
本作でもキャラクターにイキイキとした生命力を吹き込んでおり、
いくら変人ぶりを発揮していても、何だか憎めない。
ホント、くだらないパッケージに騙されず、もっと早く見ておけば良かった!
製作年:1995年
製作国:イギリス/カナダ
監督:モート・ランセン
出演:ヘレナ・ボナム・カーター、クライヴ・ラッセル、
ケイト・ネリガン、クレイグ・オレジニク、ケネス・ウェルシュ
___________________________
ティム・バートンと結婚する前のヘレナ・ボナム・カーターが、大好き。
本作も、だいぶ前から見ようとは思っていたのだが、
タイトルやパッケージに記されたあらすじを見て、敬遠していた。
B級ぽい匂いがぷんぷんしていたのだ。
~以下 パッケージに記されたあらすじの抜粋~
『脳髄を凍らせる、驚愕のエロティック・サイコ・サスペンス!』
ある事情で男を拒み続けてきたヒロイン、マーガレット
(中略)
彼女はニールとのセックスに溺れる愛欲の女に
(中略)
早過ぎるニールの死によって情念のオンナと化したマーガレットは、
彼の遺体からその男根を切断して...
ホント嘘ばっかり。
本来のあらすじから大きくかけ離れている部分を抜粋したのだが、
マーガレットには、「ある事情」というほど大それたものは、ない。
また描かれているのは新婚夫婦の純粋な生活で、
濡れ場というほどの濡れ場はワンシーンだけ。
最後に、マーガレットが切断したのはニールの男根では、ない。
このビデオを販売しているのはマクザムという会社だが
(現在も続いている会社ですぞ)、
映画ファンをなめているんじゃないかと思う。
陳腐な捏造に騙されて、作品を手に取るバカがいるとでも思っているのかしらん。
嘘をついた方が売れ行きは伸びる、と考えているところが浅はか過ぎて、
思わず冷笑してしまう。
この映画は、エロティック・サイコ・サスペンスでは決してない。
人権を軽んじられながらも家族を愛し、
必死に生き続けようとした人間の姿を描いた、炭鉱哀史だ。
舞台となるカナダ・ノバスコシア州の風景を、
全編に渡って色鮮やかに映し出しており、
鑑賞後には清々しい印象が残るほどである。
終盤のエキセントリックなエピソードが、
物語にスパイスを加えていることは確かだが、
それはあまりに無常な人生に対する、
マーガレットなりの怒り、そして悲しみの表現なのだ。
頑固で、旺盛な反骨精神に忠実なあまり、身を滅ぼしていく女は、
まさにヘレナのはまり役。
本作でもキャラクターにイキイキとした生命力を吹き込んでおり、
いくら変人ぶりを発揮していても、何だか憎めない。
ホント、くだらないパッケージに騙されず、もっと早く見ておけば良かった!

