カレンダー
| 01 | 2026/02 | 03 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
カテゴリー
こんな映画も、レビューしてます★
最新コメント
最新記事
(08/18)
(03/10)
(07/28)
(04/13)
(04/10)
最新トラックバック
プロフィール
HN:
lulabox
性別:
男性
自己紹介:
30代の編集者/ライター。ゲイ。映画、音楽大好きですが、仕事では書く機会がなく...。ので、こちらでは趣味全開にしちゃいます。
popdorianz@yahoo.co.jp
popdorianz@yahoo.co.jp
ブログ内検索
P R
カウンター
映画はエンターテインメントでありつつも、アートフォームであって欲しいと願っています。 同じような気持ちで映画を観ているひとの慰みになれば幸いです★
原題:8 femmes
製作年:2002年
製作国:フランス
監督:フランソワ・オゾン
出演;ダニエル・ダリュ―、カトリーヌ・ドヌーヴ、イザベル・ユペール、
エマニュエル・ベアール、ファニー・アルダン、ヴィルジニー・ルドワイヤン、
リュディヴィーヌ・サニエ、フィルミーヌ・リシャール

______________________
この映画をはじめて観たのはもうだいぶ前の事だが、
それほど強い印象をもったわけではない。
しかしダビングしたものを繰り返し観ているので、
やはり好きな映画ということになる。
独りでご飯を食べる時なんかには、軽くて、BGVに最適なのだ。
オゾン監督の映画にはちょっと斜めに構えたところがあって、
僕が本当に好きなタイプの監督ではない。
しかしこの映画には、8人もの女優が登場し、大立ち回りを繰り広げる。
女性上位の映画なら大好き!
僕にとって「女優」は、映画の中で非常に重要な存在なのだ。
ただの女に興味はないが、
女優~ドヌ-ヴ、ユペールのような~という存在に
賛辞を贈ることは、決して惜しまない。
映画の華として、なくてはならない存在だと思っている。
きっとオゾン監督もそうなのだろう。だからこの映画には強く共感できる。
ということで最近、この映画の限定DVDボックスを入手した。
本編は何度も観ているので、その世界をより深く識ることのできる
ボーナスディスクが目当てだ。
インタビューでは、8人の女優が製作秘話を語る。
その中からオゾン監督の姿が否応無しに浮かび上がってくるのだが、
面白かったのはドヌ-ヴの話。
そもそも役柄に不満が大きかったようで、
愚痴が口を突いて出るという感じなのだが、
その矛先はオゾン監督の演出スタンスへと向かう。
これは女優たちの意見がほぼ一致しているので事実なのだろうが、
撮影現場でのオゾン監督は「優しい暴君」のようで、怒鳴りこそしないが、
女優たちに独自の解釈や、自由な演技を認めないという。
輝かしいキャリアに相応しいプライドを持つ大女優にとって、
それなりの屈辱であることは想像に難くない。
またウーマンリヴの時代を駆け抜けてきた彼女にとって、
「女優」ではなく「女性」そのものを賞賛しない態度は、
腹に据えかねるものがあるらしい。
他の女優が朗らかに「これは女性を賛美した映画よ」と語るのとは対照的に、
ドヌーヴだけが監督への不信感を露にする。
そこに彼女の屈託が見えるようで、却って好印象を抱いた。
闘志を持たない女優に、スクリーンを飾る資格などないのだから。
屈折した役柄含め、個人的に最も気に入ったのはイザベル・ユペール。
それまであまり注目していなかったのだが、
この映画を観てから一気にファンになり、
主演作を片っ端から漁るようになった。
それほど美しくはないが、目の離せない個性を持っていて、
役者としての魅力は抜きんでている。
ここまでコメディエンヌぶりを発揮した出演作はほかにないようだが、
エキセントリックで大げさな演技が最高。
特にファニー・アルダンとの初対面シーンが傑作なのだが、
現場ではお互い乗り過ぎたようで、顔を見合わせるとつい笑ってしまう。
そんな楽しいやり取りが、NG集にはたくさん収められている。
この映画には推理劇、喜劇のほかにミュージカルの要素があり、
8人の女優がそれぞれ見せ場を持っているのだが、
選曲は監督自身が、フレンチポップス史上から行った。
僕がわかったのはユペールが歌うアルディの歌だけなのだが、
ダリダやシェイラなんかの歌も入っていたらしい。
残念なのは振付。コレオグラファーとしては素人の、
俳優による振り付けなのだが、
それだけで観賞に耐えうるものが1本もないというのは、なんとも残念。
まぁ女優=プロの踊り手ではないので仕方がない、というのもあるが、
オゾン監督からのオーダーは「誰にでも真似できる簡単な振り」だったとか。
しかし「誰もが真似する振付」というのは
まず「誰もがあこがれる振付」でなくては、と思うのだが。
メイキングシーンから得た重要な情報として、
この作品の下敷きの一つに、
ジョージ・キューカー監督の『女たち』という
映画があることがわかったのだが、
日本未公開で、字幕付きの映像ソフトも販売されていない。
同じく女性ばかりのキャストで撮影されており、
ジョーン・クロフォード辺りが出演しているらしいので、ぜひ観たいのだが...。
この映画のプロモが大々的に行われている間にも実現しなかったので、
今後も無理だろうか。
製作年:2002年
製作国:フランス
監督:フランソワ・オゾン
出演;ダニエル・ダリュ―、カトリーヌ・ドヌーヴ、イザベル・ユペール、
エマニュエル・ベアール、ファニー・アルダン、ヴィルジニー・ルドワイヤン、
リュディヴィーヌ・サニエ、フィルミーヌ・リシャール
______________________
この映画をはじめて観たのはもうだいぶ前の事だが、
それほど強い印象をもったわけではない。
しかしダビングしたものを繰り返し観ているので、
やはり好きな映画ということになる。
独りでご飯を食べる時なんかには、軽くて、BGVに最適なのだ。
オゾン監督の映画にはちょっと斜めに構えたところがあって、
僕が本当に好きなタイプの監督ではない。
しかしこの映画には、8人もの女優が登場し、大立ち回りを繰り広げる。
女性上位の映画なら大好き!
僕にとって「女優」は、映画の中で非常に重要な存在なのだ。
ただの女に興味はないが、
女優~ドヌ-ヴ、ユペールのような~という存在に
賛辞を贈ることは、決して惜しまない。
映画の華として、なくてはならない存在だと思っている。
きっとオゾン監督もそうなのだろう。だからこの映画には強く共感できる。
ということで最近、この映画の限定DVDボックスを入手した。
本編は何度も観ているので、その世界をより深く識ることのできる
ボーナスディスクが目当てだ。
インタビューでは、8人の女優が製作秘話を語る。
その中からオゾン監督の姿が否応無しに浮かび上がってくるのだが、
面白かったのはドヌ-ヴの話。
そもそも役柄に不満が大きかったようで、
愚痴が口を突いて出るという感じなのだが、
その矛先はオゾン監督の演出スタンスへと向かう。
これは女優たちの意見がほぼ一致しているので事実なのだろうが、
撮影現場でのオゾン監督は「優しい暴君」のようで、怒鳴りこそしないが、
女優たちに独自の解釈や、自由な演技を認めないという。
輝かしいキャリアに相応しいプライドを持つ大女優にとって、
それなりの屈辱であることは想像に難くない。
またウーマンリヴの時代を駆け抜けてきた彼女にとって、
「女優」ではなく「女性」そのものを賞賛しない態度は、
腹に据えかねるものがあるらしい。
他の女優が朗らかに「これは女性を賛美した映画よ」と語るのとは対照的に、
ドヌーヴだけが監督への不信感を露にする。
そこに彼女の屈託が見えるようで、却って好印象を抱いた。
闘志を持たない女優に、スクリーンを飾る資格などないのだから。
屈折した役柄含め、個人的に最も気に入ったのはイザベル・ユペール。
それまであまり注目していなかったのだが、
この映画を観てから一気にファンになり、
主演作を片っ端から漁るようになった。
それほど美しくはないが、目の離せない個性を持っていて、
役者としての魅力は抜きんでている。
ここまでコメディエンヌぶりを発揮した出演作はほかにないようだが、
エキセントリックで大げさな演技が最高。
特にファニー・アルダンとの初対面シーンが傑作なのだが、
現場ではお互い乗り過ぎたようで、顔を見合わせるとつい笑ってしまう。
そんな楽しいやり取りが、NG集にはたくさん収められている。
この映画には推理劇、喜劇のほかにミュージカルの要素があり、
8人の女優がそれぞれ見せ場を持っているのだが、
選曲は監督自身が、フレンチポップス史上から行った。
僕がわかったのはユペールが歌うアルディの歌だけなのだが、
ダリダやシェイラなんかの歌も入っていたらしい。
残念なのは振付。コレオグラファーとしては素人の、
俳優による振り付けなのだが、
それだけで観賞に耐えうるものが1本もないというのは、なんとも残念。
まぁ女優=プロの踊り手ではないので仕方がない、というのもあるが、
オゾン監督からのオーダーは「誰にでも真似できる簡単な振り」だったとか。
しかし「誰もが真似する振付」というのは
まず「誰もがあこがれる振付」でなくては、と思うのだが。
メイキングシーンから得た重要な情報として、
この作品の下敷きの一つに、
ジョージ・キューカー監督の『女たち』という
映画があることがわかったのだが、
日本未公開で、字幕付きの映像ソフトも販売されていない。
同じく女性ばかりのキャストで撮影されており、
ジョーン・クロフォード辺りが出演しているらしいので、ぜひ観たいのだが...。
この映画のプロモが大々的に行われている間にも実現しなかったので、
今後も無理だろうか。
PR
原題:Vidas Privadas
製作年:2001年
製作国:アルゼンチン/スペイン
監督:フィト・パエス
出演:セシリア・ロス、ガエル・ガルシア・ベルナル、
ルイス・シエンブロウスキー、ドロレス・フォンシ、カローナ・レイナ

_________________________________________
過去のトラウマにより、恋愛やセックスができなくなった女性が、
「お気に入りの声」をもつ男性と出逢ったことで、
再び愛情と希望に満ちた人生を取り戻しはじめる……、
というあらすじの、なかなかエキセントリックな作品。
しかし本当に訴えたかったのは、
彼女の「過去のトラウマ」自体なのではないかと思う。
なぜならそれは、単なる創作上の設定ではなく、史実だからだ。
僕は全く知らなかったのだが、
アルゼンチンでは70年代後半に軍事クーデターがあり、
以後7年間もの長きに渡って、軍部による独裁政治が敷かれてしまった。
さまざまな人権弾圧が行われ、行方不明者は3万人以上にも及ぶという。
70年代後半~80年代前半に20代だった人(この映画の主人公もそう)は、
この映画の製作時にはまだ40代という若さ。
同国内では生々しい記憶として残っていても当然なのだ。
日本に住んでいると、さほど齢の離れていない人が、
政治に人生を左右され、大きなトラウマを抱えているという事実が
実感としてわからないのだが、
それは生まれた時代がたまたま良かったというだけ。
もし世界大戦時に生を受けていたら、また第二次世界大戦で
日本が敗戦国になっていなかったとしたら、と思うと
当然他人事ではない。
ドイツナチスに関する映画は、
これまでに数え切れないほど創られてきたが、
アルゼンチンの映画人は、
今ようやくその重い口を開きはじたところなのかもしれない。
しかしこの映画の素晴らしさは、僕のように無知な者が、
観終わった後で史実を調べることにより、
さらに理解が深まるよう、注意深く作られているところ。
現代に生きる人間が映画によせる類いの関心を見越しているのが
クールだし、監督はエンターテイナーでもあると思う。
と思ったらフィト・パエスは国内でも有名な歌手で、これが初長篇作、
しかも主演のセシリア・ロスの夫でもあるというのだから、驚いた。
それにしてもラティーノ/ラティーナの生き方には、
やはりエキゾチズムがそそられる。
主人公にしても、トラウマを背負っていながら自慰に積極的なのだから、
性そのものにはオープンなのだ。
日本人の感覚からすると、性全体に背を向けてしまう方が、
無難な描き方なのでは? と思ってしまう。その相違が面白い。
一時期アルモドヴァルの緒作品や、
ビクトリア・アブリルの出演作品などを
片っ端から観ていた時期があったのだが、
もっともっとスペインやラテン・アメリカの映画が観たい。
その為に、ガエル・ガルシア・ベルナルや、ぺネロペ・クルス
といった俳優の活躍に期待したい。
製作年:2001年
製作国:アルゼンチン/スペイン
監督:フィト・パエス
出演:セシリア・ロス、ガエル・ガルシア・ベルナル、
ルイス・シエンブロウスキー、ドロレス・フォンシ、カローナ・レイナ
_________________________________________
過去のトラウマにより、恋愛やセックスができなくなった女性が、
「お気に入りの声」をもつ男性と出逢ったことで、
再び愛情と希望に満ちた人生を取り戻しはじめる……、
というあらすじの、なかなかエキセントリックな作品。
しかし本当に訴えたかったのは、
彼女の「過去のトラウマ」自体なのではないかと思う。
なぜならそれは、単なる創作上の設定ではなく、史実だからだ。
僕は全く知らなかったのだが、
アルゼンチンでは70年代後半に軍事クーデターがあり、
以後7年間もの長きに渡って、軍部による独裁政治が敷かれてしまった。
さまざまな人権弾圧が行われ、行方不明者は3万人以上にも及ぶという。
70年代後半~80年代前半に20代だった人(この映画の主人公もそう)は、
この映画の製作時にはまだ40代という若さ。
同国内では生々しい記憶として残っていても当然なのだ。
日本に住んでいると、さほど齢の離れていない人が、
政治に人生を左右され、大きなトラウマを抱えているという事実が
実感としてわからないのだが、
それは生まれた時代がたまたま良かったというだけ。
もし世界大戦時に生を受けていたら、また第二次世界大戦で
日本が敗戦国になっていなかったとしたら、と思うと
当然他人事ではない。
ドイツナチスに関する映画は、
これまでに数え切れないほど創られてきたが、
アルゼンチンの映画人は、
今ようやくその重い口を開きはじたところなのかもしれない。
しかしこの映画の素晴らしさは、僕のように無知な者が、
観終わった後で史実を調べることにより、
さらに理解が深まるよう、注意深く作られているところ。
現代に生きる人間が映画によせる類いの関心を見越しているのが
クールだし、監督はエンターテイナーでもあると思う。
と思ったらフィト・パエスは国内でも有名な歌手で、これが初長篇作、
しかも主演のセシリア・ロスの夫でもあるというのだから、驚いた。
それにしてもラティーノ/ラティーナの生き方には、
やはりエキゾチズムがそそられる。
主人公にしても、トラウマを背負っていながら自慰に積極的なのだから、
性そのものにはオープンなのだ。
日本人の感覚からすると、性全体に背を向けてしまう方が、
無難な描き方なのでは? と思ってしまう。その相違が面白い。
一時期アルモドヴァルの緒作品や、
ビクトリア・アブリルの出演作品などを
片っ端から観ていた時期があったのだが、
もっともっとスペインやラテン・アメリカの映画が観たい。
その為に、ガエル・ガルシア・ベルナルや、ぺネロペ・クルス
といった俳優の活躍に期待したい。
原題:SCHOOLDAZE
製作国:アメリカ
製作年:1988年
監督:スパイク・リー
出演:ラリー・フィッシュボーン、ジャンカルロ・エスポシート、
ティシャ・キャンベル、スパイク・リー
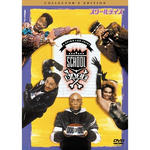
_________________________________
社会から隔絶された学生寮の中で、
独裁政治の真似事を繰り広げる学生の愚かしさを、
徹底的にパロった映画。
実社会を知らないガキ大将特有の独善的な価値観は、
程度の差こそあれ、万国共通なのだ。あたりまえだけど。
「まず内ゲバを描いていた」という事実には、感心させられる。
黒人間の意見の相違というのは、映画の中であまり見かけないからだ。
ストリートのリアルさや軽さも漂うシーンとなれば、なおさら。
本作以降「それぞれの主張の乱反射」を、
より広い世界に向け描いてきた監督の歴史を紐解くと、
ちょうど布石と呼べそうな位置にある作品なのである。
個人的に最も楽しめたのは、女性同士の対決シーン。
黒人特有のアフロヘアを誇る組と、
パーマをあて茶髪に染めた女狐組が、
ミュージカル・タッチでユーモラスに火花を散らす。
ティシャ・キャンベルってどこかで見たナと思っていたら、
『リトル・ショップ・オブ・ホラーズ』に登場した
狂言回しガールグループのフロントだった。
華があってよい。
シンガーの故・フィリス・ハイマンもカメオ出演している。
製作国:アメリカ
製作年:1988年
監督:スパイク・リー
出演:ラリー・フィッシュボーン、ジャンカルロ・エスポシート、
ティシャ・キャンベル、スパイク・リー
_________________________________
社会から隔絶された学生寮の中で、
独裁政治の真似事を繰り広げる学生の愚かしさを、
徹底的にパロった映画。
実社会を知らないガキ大将特有の独善的な価値観は、
程度の差こそあれ、万国共通なのだ。あたりまえだけど。
「まず内ゲバを描いていた」という事実には、感心させられる。
黒人間の意見の相違というのは、映画の中であまり見かけないからだ。
ストリートのリアルさや軽さも漂うシーンとなれば、なおさら。
本作以降「それぞれの主張の乱反射」を、
より広い世界に向け描いてきた監督の歴史を紐解くと、
ちょうど布石と呼べそうな位置にある作品なのである。
個人的に最も楽しめたのは、女性同士の対決シーン。
黒人特有のアフロヘアを誇る組と、
パーマをあて茶髪に染めた女狐組が、
ミュージカル・タッチでユーモラスに火花を散らす。
ティシャ・キャンベルってどこかで見たナと思っていたら、
『リトル・ショップ・オブ・ホラーズ』に登場した
狂言回しガールグループのフロントだった。
華があってよい。
シンガーの故・フィリス・ハイマンもカメオ出演している。
原題:LE HEROS DE LA FAMILLE
製作国:フランス
製作年:2006年
監督:ティエリー・クリファ
出演:ジェラルディン・ランヴァン、カトリーヌ・ドヌーヴ、
エマニュエル・ベアール、ミュウミュウ、ジェラルディン・ぺラス
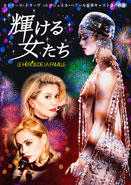
_________________________________________
邦題では「女」が前面に出ているが、
実際は落ちぶれた男芸人の再生物語。
ドヌ-ヴ、べアール、ミュウミュウの3大女優は、なんと脇役だ。
なんでこんな映画に出演したのかよくわからない……、
出演女優の中で一番おいしい所を持っていったのは、
ジェラルディン・ペラスだし。
さらに昨今のキャバレーものは、レビューや歌唱シーンを
当たり前のように切り刻むので、ホントにもったいないと思う。
実際に歌うシーンの多いべアールくらいは、
一曲ぐらいフルコーラスで見せて欲しかった。
歌手としてのプロモ出演だったとしたら、浮かばれないじゃない。
ジェラルディン・ランヴァンというのは、
フランスでは名優なのだろうか?
確かに歳の割にはきれいな身体だったが……。
老いさらばえた肉食男のロマンチシズムに共感するのってむずかしく、
終盤はやや食傷気味になった。
フランスは50過ぎても大らかにセックス・アピールを行う国らしく、
それ自体は素晴らしいし、
こういう映画があることも予想の範囲内ではあるのだが……。
平たくいうと、みじめったらしいのがイヤ。
遺言をめぐり、離散した家族が集うという設定は、
たまたま最近観た『愛する者よ、列車に乗れ』に似ていた。
当たり前のようにゲイ要素が入っているのも、同じ。
あちらが気に入った人は、この映画も気に入るかもしれない。
製作国:フランス
製作年:2006年
監督:ティエリー・クリファ
出演:ジェラルディン・ランヴァン、カトリーヌ・ドヌーヴ、
エマニュエル・ベアール、ミュウミュウ、ジェラルディン・ぺラス
_________________________________________
邦題では「女」が前面に出ているが、
実際は落ちぶれた男芸人の再生物語。
ドヌ-ヴ、べアール、ミュウミュウの3大女優は、なんと脇役だ。
なんでこんな映画に出演したのかよくわからない……、
出演女優の中で一番おいしい所を持っていったのは、
ジェラルディン・ペラスだし。
さらに昨今のキャバレーものは、レビューや歌唱シーンを
当たり前のように切り刻むので、ホントにもったいないと思う。
実際に歌うシーンの多いべアールくらいは、
一曲ぐらいフルコーラスで見せて欲しかった。
歌手としてのプロモ出演だったとしたら、浮かばれないじゃない。
ジェラルディン・ランヴァンというのは、
フランスでは名優なのだろうか?
確かに歳の割にはきれいな身体だったが……。
老いさらばえた肉食男のロマンチシズムに共感するのってむずかしく、
終盤はやや食傷気味になった。
フランスは50過ぎても大らかにセックス・アピールを行う国らしく、
それ自体は素晴らしいし、
こういう映画があることも予想の範囲内ではあるのだが……。
平たくいうと、みじめったらしいのがイヤ。
遺言をめぐり、離散した家族が集うという設定は、
たまたま最近観た『愛する者よ、列車に乗れ』に似ていた。
当たり前のようにゲイ要素が入っているのも、同じ。
あちらが気に入った人は、この映画も気に入るかもしれない。
●原題:La Prisonniere
●製作年:1968年
●製作国:フランス/イタリア
●監督:アンリ・ジョルジュ・クルーゾー
●出演:ローラン・テルズィエフ、エリザベート・ウィネル、
ベルナール・フレッソン、ダニ-・カレル、ダリオ・モレノ
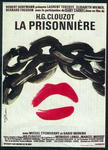
________________________________________
アンリ・ジョルジュ・クルーゾーといえば『情婦マノン』。
すごく好きな映画だ!
その監督が撮った60年代の映画があるということで、
ワクワクしながら観た。
まず画面がきれい。そういえば彼のカラー作品を観るのは初めてだ。
海辺で撮ったシーンはまるで絵画みたいで、
すごく計算されているのがわかる。
また、登場人物が当時のモダンアートに関わるアーティストたちという
設定なので、小道具がいちいちポップ。
独身貴族であり、アーティストである男の書斎が映し出されるのだが、
『女性上位時代』に勝るとも劣らない、洒脱な舞台美術に感激。
細部を創り込むことで映画のクオリティが上がる、というセオリーを
きっちりまじめに、楽しんで行っているのが伝わってくる。
さて肝心の内容はというと、これまたこの監督らしい(?)
サドマゾの世界。
といってもあからさまな性描写があるわけではなく、
精神的な従属関係を描こうとする。
自らの性向を男の存在により自覚した女が、
抵抗を試みながら、しかし、いやよいやよもなんとやらな感じで、
ついには自らを解放してしまうという、なかなか刺激的な設定なのだ。
その後ふたりは、お互いになくてはならぬ存在となるのだが……。
ちょっと残念なのは、女の方が、
それまでの従属的な愛情表現を、
なかば強引に通俗的な愛情表現へ移行しようとする、心理の描写。
全く理解できないというわけでもないのだが、
演出としてやや飛ばし過ぎなきらいがある。
この矛盾をもう少し丹念に描いてくれれば、
より凄みのある作品になったのでは、と思う。
エリザベート・ウィネルという女優は他に代表作もないようだが、
口元がやや下品で、大衆的な雰囲気だ。
しかしシーンにより美しく観えるのも事実。
前年に似たようなテーマの『昼顔』が公開されているので、
ドヌーヴの対抗馬に思い切って無名の女優を起用するというのは、
英断だったのかも。
ラストの夢のシークエンスでは、時代柄、
サイケデリックな映像美への挑戦も行われているので、
これも必見という感じだ。
●製作年:1968年
●製作国:フランス/イタリア
●監督:アンリ・ジョルジュ・クルーゾー
●出演:ローラン・テルズィエフ、エリザベート・ウィネル、
ベルナール・フレッソン、ダニ-・カレル、ダリオ・モレノ
________________________________________
アンリ・ジョルジュ・クルーゾーといえば『情婦マノン』。
すごく好きな映画だ!
その監督が撮った60年代の映画があるということで、
ワクワクしながら観た。
まず画面がきれい。そういえば彼のカラー作品を観るのは初めてだ。
海辺で撮ったシーンはまるで絵画みたいで、
すごく計算されているのがわかる。
また、登場人物が当時のモダンアートに関わるアーティストたちという
設定なので、小道具がいちいちポップ。
独身貴族であり、アーティストである男の書斎が映し出されるのだが、
『女性上位時代』に勝るとも劣らない、洒脱な舞台美術に感激。
細部を創り込むことで映画のクオリティが上がる、というセオリーを
きっちりまじめに、楽しんで行っているのが伝わってくる。
さて肝心の内容はというと、これまたこの監督らしい(?)
サドマゾの世界。
といってもあからさまな性描写があるわけではなく、
精神的な従属関係を描こうとする。
自らの性向を男の存在により自覚した女が、
抵抗を試みながら、しかし、いやよいやよもなんとやらな感じで、
ついには自らを解放してしまうという、なかなか刺激的な設定なのだ。
その後ふたりは、お互いになくてはならぬ存在となるのだが……。
ちょっと残念なのは、女の方が、
それまでの従属的な愛情表現を、
なかば強引に通俗的な愛情表現へ移行しようとする、心理の描写。
全く理解できないというわけでもないのだが、
演出としてやや飛ばし過ぎなきらいがある。
この矛盾をもう少し丹念に描いてくれれば、
より凄みのある作品になったのでは、と思う。
エリザベート・ウィネルという女優は他に代表作もないようだが、
口元がやや下品で、大衆的な雰囲気だ。
しかしシーンにより美しく観えるのも事実。
前年に似たようなテーマの『昼顔』が公開されているので、
ドヌーヴの対抗馬に思い切って無名の女優を起用するというのは、
英断だったのかも。
ラストの夢のシークエンスでは、時代柄、
サイケデリックな映像美への挑戦も行われているので、
これも必見という感じだ。

